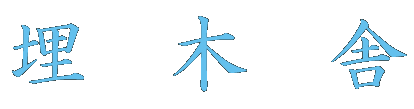児玉は自分の主宰する参謀会議をこの高崎山で行うつもりであった。
ところが、人数が多すぎることに気づいた。乃木軍関係者だけでなく、満州軍総司令部からも、
──
乃木の相談相手に。
ということで早くから少将福島安正がこの旅順の前線に来ている。大尉国司
伍七などもそうであった。さらに東京の大本営から来ている。中将鮫島さめじま
重雄や中佐筑紫つくし 熊七などがそうである。彼らの役目はすべて、乃木伊地知の頑固な
「二〇三高地軽視方針」 を修正するためのものであったが、みなこの現地に来ると、戦闘のすさまじさに眩惑され、さらには伊地知の強硬さにへきえきし、説得どころか、旅順の陣中でぶらぶらするだけの厄介者やっかいもの
のような存在になっていた。ともあれ、参謀会議に顔をつらねるべき人数が多すぎた。これだけの人数を一室に収容するだけの家屋はこの高崎山の前線にない。
「では、柳樹房の軍司令部に戻ろう」
と、気の早い児玉はこの夜、高崎山を出発した。柳樹房に着いたのは、夜九時すぎであった。児玉は疲れ切っていた。
「会議は、明日になさってはいかがでしょう」
と、田中国重少佐が見かねて言ったが、児玉は黙殺した。
会議を明日にのばすわけにはいかなかった。この瞬間でもなお、最前線にあって兵が死につつある。そのことが、児玉の心に重くのしかかっていた。彼らを長岡外史のいう
「無益の殺生」 の状態から救い出すのは、児玉による作戦大転換しかなかった。
児玉が柳樹房へ騎行しているとき、児玉のそばへ、この会議に参加する第七師団長大迫尚敏中将が追いついて来た。大迫は鞍に提灯ちょうちん
をぶらさげていた。
「大迫さんか」
児玉が声をかけた。
「ああ、閣下でございましたか」
と、大迫は馬の脚をゆるめた。
「北海道の兵は強いそうだな」
児玉は言った。
大迫は、左様でございます、強うございます、と言ったが、正確には強かった・・・・
と言うべきであろう。彼の旭川の第七師団は、旅順での部署についたときは一万五千もいたが、わずか数日の間に千人に減っていた。
「── 千人か」
児玉はしばらく闇の中を、黙って馬を進めた。伊地知から、すでに兵員の損害状況については聞いていたが、じかに当該とうがい
師団長の肉声を通して聞いてみると、印象がいっそう切実になったのである。千人というのは、少佐が指揮する大隊程度の人数であり、白いひげの陸軍中将がわざわざ指揮するようなものではない。
やがて柳樹房の軍司令部へ着くと、児玉は会議の準備を命じ、乃木の部屋で休息した。
ひどく疲れていた。
「乃木、ブランデーはないかね」
と、聞くと、乃木は、
「ある」
と、微笑し、行李のそばから一罎びん
出して来た。グラスがないため、乃木は水筒のフタを持って来たが、それよりも早く児玉は罎の口を唇につけていた。 |