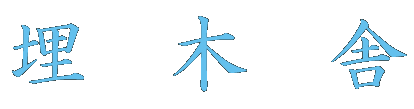「高崎山」
というこの高地は、旅順要塞の方向に向かってうねりを重ねて行くこの大丘陵群地帯の最初の隆起地であるといえる。
児玉と、乃木は、碾盤溝
という部落に入ったのが、人里の最後であった。部落を過ぎつつ児玉は、
「乃木」
と、声をかけた。児玉には碾盤溝の碾という文字の意味が分からず、乃木に聞いてみたのである。乃木はさすがに漢学の素養が深く、
「イシウスという意味じゃ」
と、即答した。なるほどそう言われてみると、高地群の間にはさまれた丸い平地で、碾盤
(石臼) のような形をしている。溝というのは、細流のことであった。
溝川程度の川が北西に向かってくぼんでおり、この水を頼りに、この小部落が生きているのであろう。
碾盤溝を過ぎると、道は坂になる。登るうちに、あちこちの山かげを利用して、乃木軍の重砲陣地がならんでいた。児玉が最初に見たのは、第一砲台であり、ついで二十八サンチ榴弾砲陣地であり、さらに第二砲台、さらに十二サンチ榴弾砲陣地などが、いくつかある。二〇三高地を主攻している第七、第一師団の司令部も、第二砲台のしばにあった。ここから、南方五つばかりの山を飛び越して二〇三高地に巨砲の砲弾を撃ち込んでいるのである。乃木軍はこれらの地帯をひとまとめにして、
「高崎山」
と、仮称していた。
「しかしどうも」
と、児玉は乃木に馬を寄せた。
「二〇三高地に射ち込むのに、ここを砲兵陣地にしていては、すこし間遠すぎやせんか」
(桂馬の横っ飛びじゃあるまし)
と、児玉は思った。二〇三高地を主攻するならするで、もっと直截ちょくせつ
に、もっと大胆に重砲の威力を発揮させる場所があるだろう。が、児玉は素人考えでそう思ったに過ぎなかった。児玉は、砲兵の出身ではなかった。
「乃木、どう思うか」
と、児玉はかさねて聞いた。
乃木の頭脳では、これについての答えはまったくなかった。ちょととまどったふうの、やや悲しげな微笑を浮かべて、
「伊地知は、よくやっとるでのう」
おt、倫理的な回答をした。乃木は伊地知をかばおうとしていた。さらに伊地知が砲兵出身である以上、伊地知が作りあげる砲兵陣地の地図を、砲兵の用兵に暗い自分がとやかくいうことはない。と乃木は決めていた。
「伊地知は、専門家じゃから」
と、乃木は言った。
(専門家もくそもあるか)
と、児玉は思った。
いかに重砲とはいえ、たかが砲弾を筒先つつさき
から飛び出させるだけの機械装置ではないか。その機械を操作せよと言われれば児玉は困るが、砲弾をどの地点から飛び出させてどこへ当てるということになれば、素人で十分以上に考えられることであり、それが用兵であった。
(この重砲陣地の位置は間違っている)
児玉は、砲兵の素人としての自分の眼識の方を、砲兵の専門家とされている伊地知のそれよりも信じた。
|