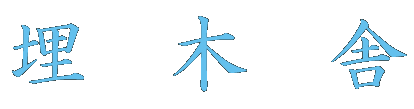結局、高崎山へ行くことになった。
高崎山は、二〇三高地から北へ直線三キロの地点に隆起している山で、かつてはロシアはここに歩兵陣地を築いていたが、去る八月十五日の強襲で、高崎山の歩兵第十五連隊が獲った山である。当時、無名の高地であった。高崎の連隊が獲ったので、その名が冠
せれらた。
児玉と乃木がめぐりあったこの曹家屯は、よほど戦場から後方である。高崎山まで十キロほどあるが、
「行くか」
と、児玉はもうシナ馬の足を動かし始めていた。シナ馬は西洋馬とは違い、脚の使い方が犬と同じで、自然、チョコチョコと歩く。乗り手は、馬上ゆたかにというふうになならず、馬が動くたびに、児玉の頭も小刻みに上下している。
これにひきかえ、乃木の馬上の姿は、見事であった。乃木はあまり兵書を読まなかったが、服装に極端に凝こ
る男で、その軍服はすべて横浜のイギリス人の仕立屋につくらせていた。ふつう偕行社で十四、五円でもあればできる将校服が、乃木の場合は二百円もかかっていた。乃木が軍人であるという意識のほとんどは、戦術戦略の研究というよりもむしろその独特の精神、服装、そして起居動作にいたるまでのいわばスタイルをどうするかということにかかっていた。乃木の軍服は、様式までが彼好みのものであった。
すでに旧式になった箱型の帽子、上衣も黒ラシャの肋骨服に白のズボンという、他の将校と違ったものであり、さらにその長靴ちょうか
も日本陸軍の制式と異なり、ひざまでおおう長大なものであった。それが、体のわりには脚の長い乃木には、よく似合っていた。
しかも乃木は、この殺人的な寒気の中で外套を用いていなかった。外套を用いないというところに乃木は自分の精神のスタイルを規定していたのかも知れなかったが、横を行く児玉にはそれが驚異であった。
「乃木、おまえ外套なしか」
と、児玉は念のために聞いてみた。
「うむ」
と、乃木は微笑した。
「まるで禅坊主の荒修業だな」
と、児玉は妙なふうに感心し、内心ひどく敬服していた。児玉は、寒がりであった。だぶだぶの外套の下に、ラッコのチッキを着込んでいる。そのチョッキは大山巌が袁世凱から贈られたもので、今度の旅順行きにあたり、大山が、
──
なにも贈るものがありませんが、せめてこれでも身につけて行ってください。
と言って、児玉に与えたものである。
馬上の児玉は、たえず鼻をこすっていた。彼はやや風邪気味で、鼻水が絶えず出た。うかつに出っ放しにすると、それが鼻の下で凍って凍傷をおこすおそれがある。
沿道、何人もの中国人の農夫にすれちがった。農夫たちは、乃木をむろん大将と思ったであろう。その横を行く児玉を、老いた従者であるかと思ったかもしれない。
|