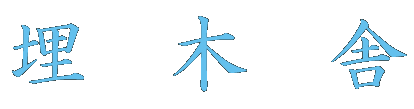二〇三高地の攻防のすさまじさにつき、ロシア側のコステンコという少将の文章を借りると、
「日本の攻城用の巨砲の猛威とその執拗な射撃は、憎悪という以外ない」
というほどであった。さらにコステンコは、日本軍の歩兵突撃のやりかたを次のような例えでえがいている。
「日本の歩兵部隊は、縦隊でやって来る。それも整然たる駈け足でやって来る」
一つの縦隊は三百人程度であった。三つの縦隊が、キビスを接してやっと登って来たことがある。最初にやって来た第一縦隊は地雷原にひっかかり、火の柱が轟然と天へあがった。やがておsの黒煙が去った時は、地上には死骸だけがころがっていた。日本軍戦法の特徴は、一つの型を繰り返すことであった。つづいてやって来た第二縦隊もまた地雷で粉砕され、さらにやって来た第三縦隊も吹っ飛ばされている。その間、時間でいえば一時間足らずであった。
信じられないほどに愚劣なことだが、本来、第一縦隊が地雷で消滅した時、現場の司令部は第二縦隊以下をいったん退却させ、砲兵陣地に連絡して地雷のありそうな場所一帯を、方眼紙のマス目を一つ一つ塗りつぶすようにして射撃させるべきであった。そういう射撃法や技術は、すでにこの当時の日本陸軍の砲兵科は十分に持っていた。それをやらず、同じ失敗を三度くり返し、千人の兵
(ロシア側の概算では、三、四千人) をむなしく消滅させてしまうというのはどういうことであろう。これは乃木の軍司令部や大迫の師団司令部だけの責任ではなく、日本陸軍の痼疾
とでもいうべきものであった。
戦略や戦術の型が出来ると、それをあたかも宗教者が教条を守るように絶対の原理もしくは方法とし、反覆して少しも不思議としない。この痼疾は日本陸軍の消滅まで続いたが、あるいはこれは陸軍の痼疾というものではなく、民族性の深い場所にひそんでいる何かがそうさせるのかも知らなかった。
むろん、砲兵力が足りないのではなかった。この時期の二〇三高地攻撃には、乃木軍はかつてないほどの砲弾をこの小さな丘に叩き込んでいる。それも攻城重砲および二十八サンチ榴弾砲という巨砲をふんだんに使った。
「その砲撃のすごさは、旅順市街にいる者でも、他の者と会話が出来ないほどであった」
と、コステンコ少将は書いている。
日本兵の突撃主義についても、いかにも直線的で、戦いに必要な狡猾こうかつ
さがない。たとえば二十七日の午後五時ごろ、日本軍の一個大隊は二〇三高地のロシア軍塹壕の一部を占領したが、この場合、ロシア軍はコンドラチェンコ少将の策によってわざと陣地をカラにして退却した。そのあと逆襲し、包囲し、壕内の日本軍をほとんど全滅させた。たしかに旅順要塞への乃木軍の攻撃法は、大きな戦術から小さな戦闘指揮にいたるまで硬直しきった精神で行われているようであった。 |