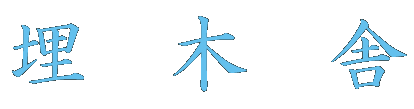この日、この方面の将であるコンドラチェンコ中将
(昇進) は、
「ワレハ、北太陽溝ノ東部シベリア狙撃兵第五連隊ノ連隊本部ニアリ」
と、その指揮所を弾丸雨飛の前線に置いた。この師団長の態度が、どれほどロシア兵士の士気を支えたかわからない。
全ロシア軍の防戦面からいっても、この時期。二〇三高地の防衛に重点をおいていた。
コンドラチェンコがステッセルに対し、
「二〇三高地に全ロシアの運命がかかっています」
と献言したことによるらしい。旅順市街の司令部にいるステッセルは、当初、この無名高地を重視していなかったことはすでに述べた。が、コンドラチェンコから教えられて次第に認識をあらため、今ではコ少将の増援要求にはほとんど無制限にこたえるようになっていた。
「この時期、二〇三高地での戦死者がもっとも多かった・・・・」
と、ステッセルの司令部つきの一士官は言っている。
「・・・・・その補充は陸軍兵で間に合わず、海軍から水兵を借りた。艦隊は湾内に尻をすえていたから、水兵はいわば手持ちだったのである。水兵の群れは、毎日、市街を通って二〇三高地へ登って行った。彼らは無邪気にはしゃぎながら後進して行ったが、どこか憂鬱そうで、足どりは重かった」
足どりの重さは、水兵用の短靴を、陸軍の重い靴にはいきかえただけではなそそうであった。先発した彼らの戦友たちはみな還って来なかった。いったんこの山に登って生還して来た者がないことを水兵たちはよく知っていたのである。それでも彼らは、この登山をいやがらなかった。この水兵の中には、十七、八歳の少年も混じっており、四十を越した老下士官もいた。老下士官のある者は、
「自分は帆船時代からセーラーだった。それが海で死なず、あの灰色の山で死ぬことになるとはなんということだ」
と、陽気に笑い声を立てた。彼らの死への後進を支配しているのは、祖国の栄光のためにとということであったであろう。しかし、どこの国の軍隊にも共通しているこういう場合、つまり死が確実である場合の進軍というのは、やや狂躁といっていいほどに陽気なものであった。
「日本人のやつは、小銃の射撃が下手だ。やつらは昂奮しすぎるからだろう。そのかわりやつらは銃剣突撃となると滅法強い」
という、敵の特性についても、この水兵たちはよく知っていた。
むろん、コンドラチェンコ中将は、補充を水兵のみに頼っていたわけではない。ほうぼうの砲台や堡塁にいる部隊の部署を機敏に転換させては、二〇三高地の防御にふりむけた。それでもこの三十日の夕刻ごろになると、そうやら支えきれなくなった。
|