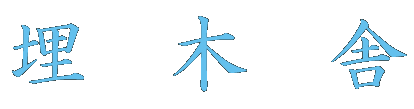児玉は、大山の部屋を訪ねることにした。
「おれは、がま坊
のもとでなら働ける」
と、渡満にあたってたれを総司令官に戴くかという時期に、児玉は、ひたすら大山説をとった。がま坊とは、大山の愛称である。容貌から来たものであろう。
あのとき、総司令官に山県有朋がなりたがった。ところが児玉は長州閥の山県とは互いに、
──
山県のジジイ
とか、児玉のジジイとか言い合っている仲であるのに、 「あの人 (山県) ほど、下で働きにくい人はいない」
と言って賛成せず、結局は児玉は自分の案どおり、薩摩人大山巌を頭に戴いて満州へやって来た。
大山巌は、幕末から維新後十年ぐらいにかけて非常な知恵者で通った人物であったが、人の頭に立つにつれ、自分を空むな
しくする訓練を身につけはじめ、頭の先から足の先まで、茫洋ぼうよう
たる風格をつくりあげてしまった人物である。海軍の東郷平八郎にもそれが共通しているところから見ると、薩摩人には、総大将とはどうあるべきかという在り方が、伝統的に型として昔からあったのであろう。
つい先ごろの沙河会戦で、激戦が続いて容易に勝敗のめどがつかず、総司令部の参謀たちが騒然としているとき、大山が昼寝から起きてきて部屋をのぞき、
「児玉サン、今日もどこかで戦ゆっさ
がごわすか」
と言って、一同を唖然あぜん
とさせた人物である。大山のこの一言で、部屋の空気がたちまち明るくなり、ヒステリックな状態がしずまったという。
大山のそう言う点について、触れたい。
彼がまだ陸軍大臣であったころ、その下に児玉源太郎、川上操六、桂太郎いた。いずれも論客で、会議になると激論が続き、決着がつきにくかったが、大山は空気のようになってそれを眺めている。やがて機会しお
をつかまえて身を乗り出し、いっさい理屈を言わず、一人一人に、
「貴公はこうしなされ、貴公はこのように」
と、それぞれに対し的確に示唆しさ
することによってたちどころに裁いた。この判定の正しさには、それがいったん下ると、理屈屋たちは理屈を言う気も起こらなくなるほどだったという。
つい、数ヶ月前のことである。
遼陽会戦が終わったとき、清国の大官の袁世凱えんせいがい
が、その配下の段芝貴だんしき
を使者にして日本軍の総司令部を訪ねさせ、見舞わせたことがある。見舞品は、毛皮、ミルク、シャンペンといったたぐいのものであった。使者の段芝貴はこのころ袁世凱の軍事秘書官長といったふうな要職にいた。大山は段を昼食に招待し、その席上、
「段サン、人間は何も知らないのにかぎります」
と、不意に言った。段はいぶかしげに大山の顔を見たが、大山は大真面目である。
「私も何も知らない人間の仲間です。何も知らなければこそ、参謀総長にもなり、陸軍大臣にもなり、大警視にもなり、はなはだしきは、文部大臣にさえなりました。何も知りませんから、どんなところにでも向きます。まことに重宝な人間ございます」
段芝貴は、生涯、大山巌に傾倒した
|