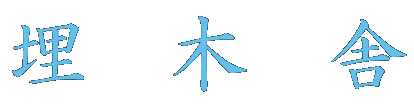日本の陸軍兵力は、底をついてしまっている。例を将棋にとると、その対局に持ち駒が必要なように、戦争にもそれが必要であった。その持ち駒が、
「予備隊」
であるということは、すでに触れた。野戦で作戦中の司令官や師団長なども、必ずその持ち駒を持ちながら駒を進めている。必要かつ決定的な戦機をつかむと、すかさずその持ち駒を打って敵の死命を制するのである。
全陸軍についても、この持ち駒が必要であった。それを大本営は後生大事に持ち、内地に控えさせていた。
第七師団
(旭川
)
第八師団 (弘前ひろさき
)
の二つの師団である。ロシアがなお本国に百万の予備軍が控えているというのに、日本は全陸軍においてわずか二個師団ざっと三万程度しか持っていないということの貧困さは、それだけでも危機であった。これが遼陽会戦前のこの年、夏までの状況である。
ところが、満州の野戦の状況といえば一戦ごとに出血はなはだしく、慢性的な兵力不足で、第七か第八か、そのいずれかを送らなければとうていロシアの大兵力と対決できないということが次第に明らかになった。
七、八月のころ、
「とにかく一個師団を送る」
ということについては、東京も現地も意向が一致した。問題はそれをどこに送るかである。
──
満州平野における主力決戦場にか。
── 旅順へか。
ということであった。
両方面とも、すでに火がついている。旅順の乃木軍司令部からは、
「とにかく送れ」
とのみ言って来ていた。
大本営ではこれを決しかねた。未決定のまま第八師団を動員し、大阪に結集、待機させた、大阪なら一令のもとに乗船させられるからであった。
戦場では、新鮮な血を欲していた。一戦ごとに減ってゆく兵力の補充については、いままで応召の後備兵を送っていた。後備兵は兵として齢とし
も長た け、妻子のある者が多く、戦士としては現役兵より相当劣るということは、この世界の常識であり、事実である。が、この内地に控えさせてきた第七、第八師団は新鋭そのものの現役兵師団であった。
「それを旅順などに送れるか」
というのが、大本営の一致した気分であった。乃木軍は戦術転換もせずに、新鮮な血だけを要求して来ている。
「日本にとっては虎の子といべきこの師団を、いたずらに無能な作戦のもとに全滅させるにしのびない」
という気分であり。参謀本部次長の長岡外史などは、
「至愚しぐ
である」
という言葉さえ使った。
が、至愚とは思いつつも、決しかねた。旅順か、満州平野かということについき、大本営では迷いぬいた挙句、異例のことながら明治帝の判断を乞うことになった。おみくじをひくような気持であったのであろう。
|