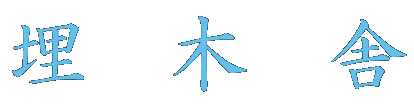長岡外史は、周到で緻密
な思考力には欠けていたが、つぎつぎに思いつきを考え出す点では、たれよりも活発であった。ひとつには大本営参謀本部が、野戦にいる児玉源太郎に作戦権のほとんどを握られていて、比較的ひまであるせいでもあった。
「旅順に気球を上げたらどうだ」
ということを思いついたのも、長岡外史であった。これは妙案であった。気球を高々と上げて観測兵を乗せ、要塞内部をのぞき込ませて砲弾の弾着を観測させるのである。長岡は後に飛行機に着眼したり、伝書鳩を鷹でやっつけようとしたりしたところを見ると、飛ぶものが好きなのかも知れなかった。
気球は、すでにヨーロッパの陸軍では実用化されていたから歴史が古いが、諸技術軽視の陸軍にあっては、明治三十四年十二月にテストしたものがあるにすぎない。長岡はこの古気球を倉庫から引き出させて、テストさせてみた。
ロープがなかったので、深川の製鋼会社に命じて作らせた。このロープが粗悪であった。この年の四月、浜離宮で上げてみると、のぼりはしたが三百メートルでロープが切れ、気球は浮游して大洗おおあらい
の海に落ちた。
とにかく気球の製造を急いでやらねばならなかった。気嚢きのう
は、芝浦芝浦製作所に命じて作らせた。これが、第三号繋留けいりゅう
気球と呼ばれるものである。
この気球隊が、七月旅順の乃木軍に参加し周家屯と鳳凰城ほうおうじょう
において空高く上った。これはわずかに役に立った。というのは旅順港内の様子や敵要塞の一部を見ることが出来tが、しかしかんじんの砲兵の観測に使えるまでには至らず、軍事的効果はほぼなかったといってよかった。これは長岡の責任ではなく、平素から気球隊を整備しておかなかった日本陸軍そのものに責任があった。
長岡は、旅順で苦慮した。
「旅順が早く陥ちねば国が亡びる」
と、毎日のように長岡はつぶやいた。
命令系統からいえば、旅順を担当している乃木軍
(第三軍) に対する直接の命令権は大山巌と児玉源太郎の満州軍が握っている。東京の大本営はその満州軍の上にあり、児玉を経ずにじかに旅順の乃木軍にあれこれ命ずることが出来ない。
が、児玉は、遼陽会戦からさらに北へと野戦軍を展開させつつあり、そのことに忙殺されていた。旅順の乃木軍をかまっているゆとりがなく、原則どおり旅順についてのすべては乃木と伊地知に任せきりであった。
このため、大本営の長岡が、命令系統を一ステップはずしてじかに乃木軍にあれこれ支援するというかたちになった。支援せざるを得なかった。乃木軍司令部のやりかたを見ていると、たれの目にも無能で無茶で、それに頑迷であったし、このままでは損害のみふえ、しかも敵要塞はびくともしていない。何か新しい奇手が必要であった。
長岡はなるほどケレン師といわれるところがあったが、こいう奇手を考える点では、うってつけの参謀本部次長かも知れなかった。ただ参謀本部次長という重職にしては彼の考えることが突拍子もないため、こととごとに失敗するだけのことであった。 |