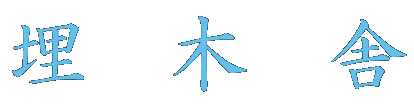陸軍の人事は山県を頂点とする長州藩が握っていることはすでに触れた。
その閥人の会には、
「一品会
」
という名がつけられていた。山口県出身の軍人で少将以上の者がこの会の会員で、陸軍という国家の機関における私的結社でこの結社がいかにおそるべき (軍人にとって)
結社であるかというと、陸軍全体の人事 ── たれを進級させるかとか、たれをどの職にもってゆくかということ ── をほとんどこの秘密会で決めていたことであった。乃木や長岡の人事もここで決められたといってよかった。
ついでながら大佐以下の山口県人は、
「同裳会どうしょうかい
」
という結社をつくっていた。同裳会は一品会のジュニア団体であり、一品会に直属していた。これらの団体は他府県出身の軍人から見れば不愉快きわまりない存在であった。
後年、これへの反動が起こり、長州閥への対抗意識から他の出世閥がうまれ、やがてそれが昭和初年、皇道派とか統制派とかいったような一見思想派ふうに見える存在に変転するのだがここではそれらは主題ではない。
要するに、長岡外史が参謀本部次長という、日本国の運命を決するかのような重職についたのは、その能力が卓絶していたからではなかった。
「長岡でもかまいませんよ」
と、山県に請合ったのは児玉源太郎である。児玉は自分以外に日露戦争をやってゆける者はいないと思っていたし、客観的にもそうであった。児玉は頭がいいといわれる長州人の長所を一身に具現していたようなところがあり、それにかつての長州志士の多くがそうであったようにつねに捨て身の覚悟でいる男で、要するに長州の伝統のすぐれた部分を継いでいた。
──
長岡でもかまいませんよ。
と言ったのは、大本営の参謀本部などはどうでもよい、と児玉は思っていた。自分が大山をかついで戦場におもむくかぎり、すべて大山と自分が戦争を刻々と処理してゆくつもりであった。このため、
──
参謀本部次長など、留守番でいい。
と思っていたに違いない。それと、兵員や兵器や弾薬の補給センター程度のしか思っていなかった。長岡でいい、と児玉がいうのはその意味であった。げんに児玉は参謀本部の出来のいい者をほとんど自分の配下として引き抜いて出たしまった。
長岡は
「世界一」 と自称する長大な八字ひげをはやしている妙な人物で、その点ではいかにもいおかがわしいハッタリ屋を想像させた。
「ケレン師である」
と、蔭口をいう者もあり、そういうところも多少はあったが、根は自分の利口と豪快さを誇示したいだけの子供っぽい性格の人物で、かつてふれたように、戦略戦術家にもっとも必要な天性の想像力はもっていた。ただその想像力はときに夢想化することもあったが、彼が将来、スキーを軍隊に導入したり、飛行機の出現当時もっともはやくそれに目をつけ、陸軍内部を啓蒙させたことなどは、彼の想像力のたくましさを証拠だてるものであった。 |