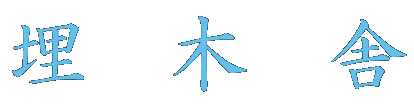乃木は東京を発つとき、
「死傷一万人で陥るだろう」
と見た。その程度でしか旅順を見ていなかった。それを基準として攻撃法を決めた。むろん、参謀長の伊地知幸介の頭脳から出たものである。
ところが第一回の総攻撃だけで日本軍の死傷は一万六千にのぼるというすさまじい敗北に終わり、しかも旅順を陥すどころか、その大要塞の鉄壁にはかすり傷ひとつ負わせることが出来なかった。要塞側の圧倒的な勝利であった。しかもその乃木軍はその攻撃法を変えず、第二回目の総攻撃をやった。同じ結果が出た。死傷四千九百人で、要塞は微動だにしない。
「すでに鉄壁下に二万余人を埋めてみればなんとか攻撃方法を考えそうなものである」
と、東京にいる参謀本部次長長岡外史は、その日記で乃木と伊地知のコンビへのいきどおりを含めて書いている。
第一回の攻撃で、一個師団に匹敵する大兵力が消えてしまったということについては、東京は寛大であった。寛大であるというよりも、
「旅順はそれほどの要塞か」
ということを、この大犠牲を払うことによって東京自身が認識したのである。この錯誤と認識は戦争にはつきものであった。しかし東京の長岡外史らが、乃木軍参謀長の頭を疑ったのは、この錯誤を少しも錯誤であるとは思わず、従ってここから教訓を引き出して攻撃方法の転換を考えようとはしなかったことであった。
要塞ならば、当たり前のことであった。伊地知は一万数千の犠牲を払ってこの程度の、百科事典の
「要塞」 項目程度の知識を得た。しかもその知識は、彼ら参謀が前線へ挺身
して得たものでなく、 「諸報告を総合」 して得た。
「第三軍司令部は、敵の砲弾がとても届かぬほどの後方に位置している」
というのは、すでに評判であった。
乃木
希典はこれを気にし、のちに、
「もっと前へ出よう」
と伊地知に提言したが、伊地知はそれでは冷静な作戦判断が出来ない、として彼の独自の距離を固執した。
乃木はべつに臆病でこのような位置にいたのではない。彼自身は、しばしば砲弾の炸裂する前線へ馬を立て、士気を鼓舞した。が、乃木がいかに前線の惨況をその目で見ても、彼自身が作戦を立てるわけではなかった。ついでながら第一軍から第四軍までの司令官のうち参謀の助けを借りずに戦が出来るのは奥保鞏やすかた
だけであるとされていた。とくに作戦畑に一度も籍を置いたことがない乃木にとっては、伊地知を信じてその言葉を用いて行くしかなかった。
「仁なれば厳ならず」
と、この戦場で第十一師団の大隊長として参加した大沢少佐は、乃木を仁者として崇敬しつつも。仁者であるのあまり乃木が゙伊地知以下の幕僚に対して、寛仁でありすぎたことを残念がっている。伊地知が得る前線状況は、多くは第一線の青年将校からのまた聞き
(階級的段階をへての) であった。乃木はそれでも苦情を言わなかった。乃木は金州で長男を失い、のちにこの戦場で次男を失い、さらに彼自身も出征の当初から死を決意していたが、彼の最大の不運はすぐれた参謀長を得なかったことであった。 |