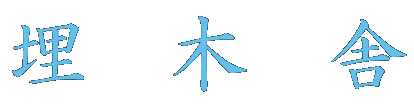椃弴偺峘偲偦偺戝梫嵡偼丄擔杮偺棨孯偵偲偭偰偺嵟戝偺捝揰偱偁傝丄偁傝偮偯偗偰偄傞丅
搶嫿偺娡戉偼丄斶溒傪捠傝墇偟偰偙偭偗偄偱偁偭偨丅斵傜偼棨孯偑梫嵡傪偍偲偝側偄偨傔丄側偍傕偙偺峘偺岥奜偵揃偯偗偝傟丄儘僔傾偺巆懚娡戉偑弌偰棃偰奀忋傪峳傜偟傑傢傞偙偲傪杊偖偨傔斣恖偺栶栚傪偮偯偗偰偄傞丅戝愴棯偐傜尒傟偽偙傟傎偳偺楺旓偼側偔丅偙傟傎偳擔杮偺彑攕偵娭偟偰偁傇側偄忬懺偼側偐偭偨丅
劅劅
僶儖僢僠僋娡戉偼偄偮弌偰偔傞偐丅
偲偄偆曬偼丄墷廈偐傜偺忣曬偼傑偪傑偪偱側偩妋曬偼側偄丅柍偄偵偟偰傕丄
乽憗偗傟偽廫寧偵擔杮奀偵尰傟傞乿
偲偄偆愴溕偡傋偒愢傕偍偙側傢傟偰偄偨丅
偟偐偟側偑傜椃弴偼暥帤捠傝揝暻偱丅婫愡偼偡偱偵壞偑夁偓傛偆偲偟偰偄傞丅偄傑偐傝偵椃弴偑偍偪偰傕
(偦傟偼柌偩偑) 娡戉偺廋棟偵偼嵟掅擇儢寧偼偐偐傞偺偱偁傞丅
奺娡傪廋棟偟偰婡擻傪夞暅偝偣偹偽丄偲偰傕僶儖僠僢僋娡戉偵彑偰傞尒崬傒偼側偄丅偄傑娮偪偨偲偙傠偱丄偓傝偓傝
(廫寧愢偲偡傟偽) 偱偁偭偨丅奀孯偼丄偁偣偭偨丅
搶嫗偺戝杮塩傕丄偁偣傝偵偁偣偭偨丅
乽擳栘偱偼柍棟偩偭偨乿
偲偄偆昡壙偑丄偡偱偵弌偰偄偨丅嶲杁挿偺埳抧抦岾夘偺柍擻偵偮偄偰傕丄擳栘埲忋偵偦偺昡壙偑寛掕揑偵側傝偮偮偁偭偨偑丄偟偐偟偦偆偄偆恖帠傪峴偭偨偺偼搶嫗偺嵟崅巜摫晹偱偁傞埲忋丄偄傑偝傜偳偆偡傞偙偲傕弌棃側偄丅峏揜愢
傕堦晹偱弌偰偄偨丅偟偐偟愴偄偺宲懕拞偵巌椷姱偲嶲杁挿傪曄偊傞偙偲偼丄巑婥偲偄偆揰偱晄棙偱偁偭偨丅
乽偁偺嶌愴偱偼丄巑懖傪戝検偵搳偠偰偼椃弴偺偆傔憪偵偮偐偭偰偄傞偩偗偱丄椃弴偦偺傕偺偼傃偔偲傕偟偰偄側偄丅偄偭偨偄壗傪偟偰偄傞偺偐乿
偲偄偆斸昡傕丄戝杮塩偱偼弌偰偄偨丅嬃扱偡傋偒偙偲偼丄擳栘孯偺嵟崅姴晹偺柍擻傛傝傕丄柦椷偺傑傑偵栙乆偲杽傔憪偵側偭偰巰傫偱峴偔偙偺柧帯偲偄偆帪戙偺柍柤擔杮恖偨偪偺壏弴偝偱偁偭偨丅
劅劅
柉偼樳傛 傜偟傓傋偟丅
偲偄偆摽愳昐擭偺晻寶惂偵傛偭偰偮偪偐傢傟偨偍忋偐傒
傊偺晐偍偦 傟偲悘弴偺旤摽偑丄柧帯嶰廫擭戙偵側偭偰傕暫巑偨偪偺娫偱側偍幐傢傟偰偄側偄丅柦椷偼愨懳偺傕偺偱偁偭偨丅斵傜偼丄堦偮妎偊偺傛偆偵孞傝曉偝傟傞摨堦栚昗傊偺峌寕柦椷偵栙乆偲廬偄丄嫄戝側嶦恖婡夿偺慜偱抍懱偛偲丄懇偨偽
偵側偭偰嶦偝傟偨丅
偟偐傕擳栘孯偺巌椷晹偼偮偹偵屻曽偵偁傝偡偓丄庒偄嶲杁偑慜慄偵峴偔偙偲傕婬偱丄偙偺嶴忬傪姶妎偲偟偰抦傞偲偙傠偑偵傇偐偭偨丅偙偺揰丄偙偺峌埻愴偺嵟屻偺抜奒偱丄帣嬍尮懢榊偑偙偺愴慄偵尰傟偨偲偒丄傑偢偙偺揰偵寖搟偟偨丅帣嬍偼擳栘偵懳偟偰偼姲梕偱偁偭偨丅擳栘偵偼偨偩慡孯傪摑屼偡傞偲偄偆偩偗偑丄婜懸偝傟偰偄偨丅
偑丄幚嵺嶌愴傪峴偆傋偒埳抧抦嶲杁挿埲壓偺嶲杁偵懳偟偰偼捝攍偟偨丅堦嶲杁偑偁傑傝偵愴嫷傪抦傜側偄偲偄偆偺偱偦偺嶲杁寽復傪丄廜恖偺慜偱堷偒偪偓偭偨偙偲傕偁偭偨丅偨偩偟帣嬍偑忔傝弌偟偨偺偼枛婜偺偙傠偱丄偙偺帪婜丄柦椷宯摑忋丄偡傋偰偼擳栘孯偺嵸検偵擟偝傟偰偄傞丅
|