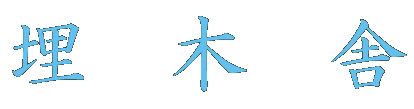ついでながら、さきにマカロフがこの朝、どういう訳か、勇敢でありすぎた。そう書いた。というのは、彼は出港に当っての重大な習慣を忘れた。ということであった。港口の掃海をしなかったのである。
いつの時も、マカロフは小艦艇を先に走らせ、海面下に沈置された機械水雷を取り除けさせてから乗り出した。それが海軍指揮官としての当然の配慮であったが、この日、マカロフは自軍の駆逐艦一隻が日本の駆逐艦四隻に袋叩きにあったことに先ず憤慨した。彼は一等巡洋艦バヤーンに駆逐艦を救助させるべく突出させた。ところが悪いことにそのバヤーンも、突如現れた日本の巡洋艦隊の挑戦を受けた。バヤーンは単艦で戦いつつあったが、この様子をマカロフは知り、その闘志がどうにもならぬほどの憤激に変わった。彼は掃海をしなかった。ともかく一秒でも早く戦場におもむくべく急航したのである。
現場に着くとそこへ東郷の主力艦隊が出現した。マカロフはやむなく退却を命じ、艦尾砲をもって砲戦を交えつつ、東郷を要塞砲の射程内に引き込もうとした。いかにもマカロフらしい軽快さを持った艦隊指揮であった。
(さすがマカロフだ)
と、三笠の艦上から真之は感嘆する思いでその光景を見ていた。
三笠以下の戦艦は、射程の届く限り戦艦ペトロパウロウスクへ砲弾を送ったが、一弾がわずかに命中したのみで、他は水中に落ち、そのうちマカロフは東郷を引き離してしまった。
(あ、おなじ回帰運動をはじめた)
と、真之は肉眼で遠望しながら思った。
東郷は、双眼鏡で見ている。他の幕僚も、東郷の双眼鏡ほど倍率は高くなかったが、マカロフ艦隊の後を注視しつづけた。
艦の運用はマカロフの責任ではない。艦長ヤーコレフ大佐の仕事であった。艦はいつものように老虎尾
半島の山脈に平行しつつ速度をおとして海岸沿いに進み、旅順の港口を目指した。
戦闘終了の鐘が鳴った。
水兵たちが砲側から離れ、甲板のあちこちで足をのばしはじめた。
マカロフは戦闘指揮所を出たとき、たまたまそこにいた従軍画家のウェレシチャーギンに気づき、陽気に声をかけた。
「うまく写生できましたかね」
と言うと、画家はスケッチブックから目をあげ、それが提督であることに気づくと、ちょっとはにかみながら両手でスケッチブックをかざしてみせた写生帳の水平線上に、日本艦隊が描かれていた。
現実の水平線上にも、日本艦隊がいた。空を幾すじもの煙が染めている。
そのとき天地が裂けたかと思われるほどの轟音が起こり、艦底が持ち上がり、甲板が大きくかしぎ、大火柱があがった。すべてが同時だった。マカロフは爆風の為に飛ばされ、甲板に叩きつけられた。 |