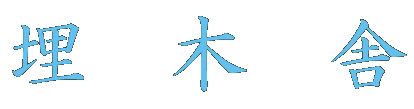日露戦争というのは、世界史的な帝国主義時代の一現象であることにまちがいない。
が、その現象の中で、日本側の立場は、追い詰められた者が、生きる力のぎりぎりのものをふりしぼろうとした防衛戦であったこともまぎれもない。
話は、飛ぶ。
日本の政府要人というものが、戦争の勝敗にどの程度の自身を持っていたかということについて触れたい。そのためには、金子堅太郎
というすでに司法大臣などにも任じたこの当時の二流要人に登場してもらわねばならない。
ついでながら金子堅太郎は、福岡県人である。維新後ほどなく郷党の先輩である平賀義質よしただ
という官員をたよって上京し、平賀家の書生として住み込んだあたり、明治の人生のひとつの典型と言っていい。
明治初年の官員というのは、人によってちがうにしても、四民平等になったというような意識がまったくなかった人物が多い。司法省の平賀義質もそうであり、書生の金子を、徳川時代の中間ちゅうげん
のようにして遇した。登庁するとき、金子に挟箱はさみばこ
をもたせて供をさせる。退庁のときは庁舎の玄関先にすわらせ、土下座の礼をとらせる。このことが、すでに開化意識を持った金子には耐え難かったらしい。
明治三十三年、伊藤内閣の司法大臣になったとき、彼は司法省の玄関に立ち、しずかに属僚をかえりみて、
「自分は少年の頃、この玄関に土下座をして草履ぞうり
取りをした。今その省の大臣になった自分を思うと、往時を思い、今時を思い、万感が胸に迫る思いがする」
と、言った。彼のいう万感胸に迫るというのは明治人が何の疑いもなく持っていた立身出世の意識が、一種詩情のかたちであらわれていて、、これまた一典型としておもしろい。
金子は書生時代、外国留学の機会を得て渡米した。留学先はアメリカであり、ハーヴァード大学で法律を学んだ。その時の同窓が、いまアメリカ合衆国の大統領になっているセオドア・ルーズベルトであった。
日本政府が対露開戦を決意したのは明治三十七年二月四日の最後の御前会議においてであったが、その会議が終わると、枢密院議長伊藤博文が金子堅太郎を呼び、
「じつは、今開戦に決まった」
とうちあけた。伊藤は泣きはらしたような目をしていたというから、日本の勝利はほとんど信ずることが出来なかった伊藤は、この決定に無量の思いがあったのであろう。
伊藤が金子に言うには、
「米国へ行ってもらいた。米国大統領と米国民の同情を喚起し、ほどよいところで米国の好意的な仲介により停戦講和というところへ持ってゆけるよう、その工作に従事してもらいたい」
ということであった。金子堅太郎には自信がなかった。日露が戦えば勝つのはロシアに決まっているではないか。 |