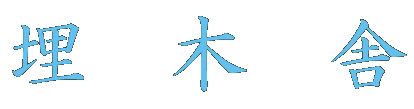この小説をどう書こうかということを、まだ悩んでいる。
子規は、死んだ。
好古と真之は、やがて日露戦争のなかへ入ってゆくであろう。
出来る事なら彼らをたえず軸にしながら日露戦争そのものを描いてゆきたいが、しかし対象は漠然として大きく、そういうものを十分にとらえることが出来るほど、小説というものは便利なものではない。
だから、時には主人公たちから離れねばならない。このため、かつては紙数が多すぎるほどロシアとその事情と、ニコライ二世のことに触れた。
なぜならば日露戦争をおこしたエネルギーは歴史そのものであるとしても、その歴史のこの当時のこの局面での運転者の一人が、ニコライ二世であったからである。
どちらがおこしたか、という設問はあまり科学的ではない。しかし強いてこの戦争の戦争責任者を四捨五入して決めるとすれば、ロシアが八分、日本が二分である。そのロシアの八分のうちほとんどはニコライ二世が負う。この皇帝の性格、判断力が、この大きなわざわいを招いた責任を負わなければならない。このためにニコライ二世のことに多くの紙数を割いた。
さて、日本側である。
日本側の政治家のほとんどは、ロシアと戦って勝てるとは夢にも思わなかった。日本の代表的政治家である伊藤博文は、恐露家というあだなをもらっていた。
伊藤は、恐かったであろう。彼は幕末においては長州の吉田松陰の門人の一人として、尊皇攘夷の志士であった。末輩の志士であったが、幕末の長州騒乱のほとんどをつぶさに体験した。文久三
(1863) 年には長州藩が下関海峡を通る外国艦船を攘夷と称して砲撃したときは、彼はロンドンにいた。タイムズを見てすぐ帰国したが、彼が見たのは、敗戦の新戦場であった。
長州は、幕府の第一次長州征伐においても藩がいま少しで滅亡であろうというぎりぎりの段階までおしつめられた。たまたま薩摩と手を握ることによって奇跡的な起死回生を遂げたが、それらの困難をつぶさにながめたために、伊藤は、天性の上にすぐれた外交上の思考法と感覚を身につけた。幕末、長州は薩摩と手を握って死の寸前から生きかえって勝利者の位置を占めたが、日本の運営者の一人である今日、薩摩の役割を果たすべき同盟者が必要であった。他のひとびとはそれを英国にしようとしたが伊藤はロシアを主張した。
ロシアが、極東を侵略し、圧迫している。その圧迫者と手を握ることによって、侵略と圧迫から逃れようとするのが伊藤の案であったが、これは当局者から取り上げられず、結局は英国と同盟した。
さて、軍部はどうか。 |