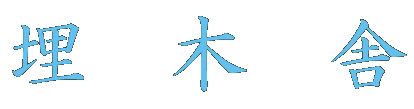月明の下で、虚子はいそがしく下駄音をたてた。碧梧桐と鼠骨に子規の死を知らせ終わると、虚子は引き返した。
足が、重くなった。
(もどりたくない)
と、思った。もどっても子規はすでにむくろになったいるし、母親のお八重や妹のお律の嘆きの中にいることは、居ることすら無残な感じがする。
しかし、もどらねばならない。すでに正岡家は女二人が残されているだけであり、葬儀やらあと始末やら、なにもかも虚子たちがやらなけれなならない。
右手が竹垣だが、左手は加賀屋敷の黒板塀がつづいている。月の光は、その板塀いっぱいにあてっていて、その板塀だけを見ていると、夜とも思えぬほど明るかった。
その板塀の明るさの中を、何物かが動いて流れて行くような気が、一瞬した。子規居士の霊だと、虚子は思った。霊が今空中へあがりつつあるのであろう。
子規逝
くや 十七日の 月明げつめい
に
と、虚子が口ずさんだのは、この時であった。即興だが、こしらえごとでなく、子規がその文学的生命をかけてやかましく言った写生を虚子はいま行ったつもりだった。
帰ると、お八重もお律も、子規の遺骸のそばでぼんやりしている。
お八重はさきほど、涙ひとつこぼさなかったが、たたきに下駄をぬぎすてて座敷に上がって来た虚子の姿を見ると、急に心の支柱が崩れる思いがしたらしい。
「キヨシさん」
と、お八重は虚子に呼びかけながら、そのくせ虚子の方を見ず、顔を横に向け、暗い壁を見つめたなりの姿勢でいる。
虚子はすわった。黙っていると、お八重は顔を伏せた。泣くまいとしているようで、そのこらえが、小さな肩に出ている。
「升のぼる
は、キヨシさんがいちばん好きでした。キヨシさんには、ひとかたならぬお世話になりました」
お八重は、子規にかわって、こういうかたちで礼を言いたかったのであろう。言いおわると、肩の震えを激しくした。しかし声はついに立てなかった。
虚子は黙っていた。皆が来るまで、黙っているしかないと思った。ただときどき、子規の遺骸を見た。
(あなたがのぼってゆくのを、いまあし・・
は見たぞな)
と、虚子は内緒ごとのように子規に告げてみた。
ふと、子規の歌を思いだした。
世の人は 四国猿とぞ 笑ふなる
四国の猿の 小猿ぞわれは
子規は、自分が田舎者であることをひそかに卑下していたが、その田舎者が日本の俳句と和歌を革新したぞという叫びたくなるような誇りを、この歌にこめている。子規は辞世をつくらなかったが、彼の三十五年の生涯を一首があらわしているようにも、虚子には思えた。
|