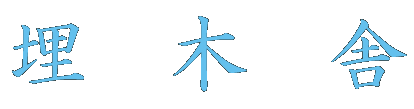予定戦場は、ジューバのカリブ海である。
ワシントンの海軍司令部の壁には、カリブ海の大海図が掲げられている。
そこまではスペインのマドリッドの海軍司令部でもそうであろう。大海図も掲げずに、一少将に艦隊だけを与えて送り出したということはあり得ない。
が、ワシントンの場合は、その大海図に点々と軍艦のピンがおされている。軍艦が移動するごとにそれが動く。敵のセルベラ艦隊の所在も、情報があるごとにピンが動く。これによってたれの目にも状況把握が一目瞭然
であり、状況さえ明らかであれば、次に打つべき手 ── たとえば艦隊の集散、攻撃の目標、燃料弾薬の補給など ── ということは、どういう凡庸な、たとえば素人のような参謀でも気がつく。要するに作戦室の全員が、書記ですら、刻々の状況を頭に入れてそれぞれの分担を処理している。組織を機能化することは、彼ら開拓民の子孫たちの得意とするところであった。
いっぽう、スペインのセルベラ艦隊はどうであろう。
セルベラ少将は、四月、ポルトガル領カボ・ベルデ群島のサン・ヴィセン港で艦隊の集結を待っていた。
二十九日、深夜、出港。わざと出港を深夜にしたのは、むろん艦隊行動の秘匿ひとく
のためである。出港の前夜、セルベラ少将は本国に向け電報を発した。
「明朝イヨイヨ出撃ノ予定。安ラカナル良心ヲモッテ、ワレハイケニエ (犠牲)
ニオモムク」 (島田謹二教授訳)
恨みを込めている。
本国政府の無能、無策、怠慢などすべての政治的悪徳のしわ寄せが、セルベラの艦隊に集まっている。勝つための条件を少しも整えてくれない政府に対し、死の実務家が放った最後の恨みの言葉であった。
ついでながら日露戦争のロシアは、この当時のスペインに比べてはるかに大国であり、その陸海軍は巨大であったが、しかし国家が老衰し、政府は腐敗し、国民が勝壮気を失っていたという点では、この時期のスペインとそっくりであった。さらにはその相手が組織がみずみずしく動くという新興国家である点でも、そっくりであった。セルベラ少将の出港のときの心境は、後年バルチック艦隊の乗組員が本国を出発するにさいして持った心境と型としてひどく似かよっている。
さらに似ているのは、その長大な遠征航海にあるであろう。大艦隊をひきずって戦場へ向けて長大な航海をする場合の司令官の苦心というものは、それをやった者でなければわからない。セルベラの苦悩は、後年のバルチック艦隊司令長官ロジェストウェンスキーがただ一人理解し得るものではないか。
セルベラの艦隊は、のろのろと進む。針路は一路西であり、熱帯のしかも酷暑の季節であり、艦内生活の苦しさは、古参の海員すら音ね
をあげるほどであった。
二十余日の航海をへて、五月十九日、彼らはキューバのサンチアゴ港に入った。この情報はすぐさまスパイによってワシントンのアメリカ海軍司令部に送られ、同司令部は時をうつさず、キューバのまわりで索敵行動をしているサムソン少将の艦隊に知らせた。
サムソンは海上決戦をのぞんだが、セルベラはそれを嫌った。サンチアゴ軍港の奥深くにひそみ、軍港の要塞砲に頼って艦隊を保全しようとした。この方針は、日露戦争におけるロシアの旅順艦隊の場合と同じであった。
「出て来ないなら、閉じ込めてしまう」
というのが、アメリカ側の考え方である。セルベラ艦隊に、うろうろされるのは困る。アメリカとしては陸軍を送る海上輸送が出来ないからである。敵を沈めるのが最上であるが、熊が穴に入ったように出て来ないとなると、岩穴の入口に火器をそろえて出ぬようにしてしまう。
それが、封鎖作戦である。先にふれたように、日露戦争のとき東郷艦隊が旅順に対してやったのろ同じことをアメリカはした。日米海軍は偶然ながら同一経験を持った。 |