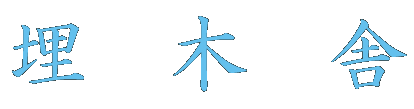日
清 戦 争 (四十七) | このあたりを、土城子という。
好古は、兵をふた手にわけた。騎兵第一中隊は全員下馬させ、徒歩兵にし、本道の東側に散開させて進ませた。
第二中隊に対しては、乗馬戦をさせるべく本道の西側を進ませた。べつに自分の手もとに歩兵中隊を置き、予備隊とした。
──
兵隊の数が足らん。
と、好古は思った。足らぬどころか圧倒的に不足していた。敵は歩兵一個旅団であり砲まで備えている。それが、わが方の攻撃を見てゆうゆう応戦に態勢を整え、射撃を始めた。すざまじい銃砲声が天地に満ち味方は横なぐりの夕立をかぶったようになった。
好古は、かわっていた。
水筒に酒を入れてある。シナ酒である。草むらに腰を下ろし、片手にオペラグラスを持ち、片手に水筒を持って飲みはじめた。
──
いくさ酒というものは、妙な味がする。
と、晩年も言った。どういう味がするのか、それは説明しない。
彼は後年、日露戦争の戦場でもそうであったが、コサック騎兵団の怒濤
のような襲撃の中で酒を飲んだ。激戦となると必ず飲む。飲んで勇気をつけるというのではない。この大酒家は、飲んだからといって頭に血が上って景気づくというぐあいにはならず、ただ、鎮静はするらしい。頭に血が上ろうとする時、酒を飲むことによってあたりまえの自分を維持することが出来る。
戦況は、のっけから不利である。時がたつに連れていよいよ不利になってきた。
(兵が萎縮いしゅく
している)
と、好古はそう見た。どの兵もせいいっぱいの勇気をふるって射撃運動作をくり返しているが、将校も兵も一針つけば泣き出しそなくらいに緊張、というよりも硬直しきっていた。
こういうばあい、指揮官の精神がどういうぐあいであるかを、味方に見せてやらねばならない。その意味では、いくさは指揮官にとって命がけの演技であった。
「前へ出るけんの」
と、好古は馬の乗り、その高姿勢のまま前へ進めた。副官が狂ったように馬の口にとりすがったが、好古は行くのみである。馬上で水筒をラッパ飲みしている。ゆうゆうと進め、ついに最前線に伏射中の兵のあたりまで出た。弾が好古のまわりの砂をあげ、肩をかすめ、頭上に鳴った。頭上に鳴る小銃弾は当ることはないが、地面へつきささる弾が多くなると敵弾の命中率は高くなってくる。
「まったく、たいへんなんだ」
と、徒歩兵の散兵を指揮中の第一中隊長河野政次郎大尉が、あとでいうのに、
「顔つきもかわっていねば、様子も変わらない。恐怖もあせりも困惑もなく、ちょうど酒客が盃をかたむけつつ満開の花でもながめているよう」 であった。
たちまち兵たちの顔色に血の色が戻ったが、戦勢はとうてい回復しそうになく、敵はいよいよ迫って来る。 |
|
|