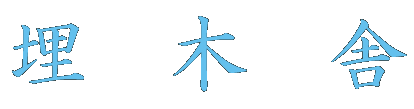広島でのことである。好古は指揮刀を吊っている、町ですれ違った同期の歩兵大尉が、
「なんだ、その腰は」
と、おどろいた。指揮刀のことである。
指揮刀は玩具のような刀身で、刃がなく、当然ながら切れない。将校は平時、いわばかざりと指揮用のために指揮刀を吊る。しかし戦時は軍刀にかえる。軍刀はサーベル式に拵
えられているが、なかみは日本刀であり、それが制式になっている。要するに好古は平時のままであった。
「これでいいんだ」
と、好古はそのまま別れた。隊の宿舎に帰ると、部下の曹長が不安気に同じ質問をした。
不安がるのも、当然であった。騎兵には突撃ということがある。馬をつらねて敵中に飛び込み、刀か槍
(日本騎兵には槍はない。ヨーロッパの重騎兵や清国の騎兵にはそれが武器になっている) で、刺突して戦わねばならない。指揮刀ではいわば竹光と同じであり、突いても敵の衣服を突き通すことは出来ず、ふりかぶっても敵を切ることは出来ない。第一、護身のための武器が玩具では不安で戦の場に立っていられないではないか。
「いや、ええんじゃ」
と、好古は言った。
このあたりが、この人物の奇妙なところであろう。彼はのちの日露戦争にも腰にこの指揮刀を吊って戦場を往来した。理由は言わない。
理由を言わなかったが、おそらく指揮官の役目は個人で敵を殺傷するものではなく一隊一軍を進退させ敵を圧倒するところにある、によって個人としての携帯兵器はいらない、というようなことであったのかもしれない。
それ以外にも理由がありそうである。好古は同時代のあらゆるひとびとから、
「最後の古武士」
とか、戦国の豪傑の再来などと言われた。しかし本来はどうなのであろう。
考える材料が二つある。ひとつは、彼は他の軍人の場合のようにその晩年、自分の子供たちを軍人にしようという気持はさらになかった。福沢諭吉の思想と人物を尊敬し、その教育に同感し、自分の子供たちを幼稚舎から慶応へ入れ、結局普通の市民にした。
いまひとつは、彼が松山で送った少年の頃や大阪と名古屋で暮らした教員時代、ひとびとは彼からおよそ豪傑を想像しなかった。おだやかで親切な少年であり、青年であったにすぎない。それが、官費で学問が出来るというので軍人になった。軍人になると、国家は彼にヨーロッパ風の騎兵の育成者として期待し、彼もそのような自分であるべく努力した。
彼は自己教育の結果、
「豪傑」 になったのであろう。戦に勝つについてのあらゆる努力を惜しまなかったが、しかし彼自身の個人動作としてその右手で血刀をふるい、敵の肉を刺し、骨を断つようなことはひそかに避けようとしていたのではないか。
むろんそのために竹光を腰に吊るということは、よほどの勇気が要る。勇気はあるいは固有のものではなく、彼の自己教育の所産であったように思われる。 |