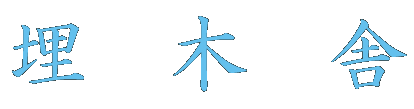参謀次長川上操六の諜報網からすれば韓国や清国の大官の動きは、対日問題に関する限り手に取るように明らかであったろう。彼は東京にいながら、すべてを知っていた。
韓国が清国に内乱鎮圧のための出兵を要請したその翌日、東京では日本も出兵するという旨を閣議が決定したことはすでに述べた。しかも、単に出兵
であり、戦争を起こすということではない。閣議は、 「韓国における日清両国の勢力均衡を維持し」 という。勢力均衡の外交思想は英国の伝統思想であり、日本はそれを英国から学んだ。さらに閣議は言う、
「なるべく平和を破らずして国家の名誉を保全する」。
「出兵」
というのは、むろん無法の出兵ではない。準拠すべき条約があった。明治十五年八月三十日、韓国との間に結ばれた済物浦さいもつぼ
条約がそれである。
「日本公使館は兵員若干・・
をおき、護衛すること」
という条文があり、それによって出兵・・
する。
が川上操六はそういう意味での出兵には満足できなかった。彼と同思想を持つ者は外務大臣陸奥宗光である。
陸奥も、多年、韓国において清国のために外交上の圧迫を受けつづけているということの現状を打破するには、砲弾による解決法のほかないとしており、戦えば勝つという自信もあった。日本政府は連年国会の内外において在野勢力の攻撃を受け、いまや収拾のつかぬまでになっている。陸奥にすれば開戦によって在野勢力の視点を外に転じせしめようとも思った。
この六月二日の閣議のあと、川上操六はひそかに陸奥をその官邸に訪問し、密談した。
川上は言った。
「自分が得ている情報から判断するに、清国はすでに韓国に五千の兵を駐在させている」
──
ところで日本は。
と、川上は言う。これに対して少なくとも七、八千の兵は動員せねばならぬ。
「勝算は如何いかん
」
と、陸奥。
「たとえ漢城付近で衝突するも、撃破することは易々いい
たるものである。むろん、清国はわが出兵を聞いて急ぎ増派するに違いない。そうなればわが軍もそれにつれて増派してゆく」
「要するに初動の兵数は七、八千だな」
「左様、最低の人数である」
「しかし、伊藤首相は許すまい。彼は頭からの平和主義者である」
「そこを、ごまかすのだ」
と、川上操六は言った。
「首相に対しては一個旅団を動かす、と言っておく。一個旅団の兵数は二千である。これならば首相も許す」
「それで?」
「二千は平時の兵数である。しかし、旅団が戦時編制をすれば七、八千になる。首相はそこまで気づかぬはずだ」
川上がみるように、首相伊藤博文はこの日清間の出兵問題が戦争にまで飛躍することを恐れ続けた。
六月二日の閣議が終わってから伊藤は川上を呼んでこの点を問いただしている。
「どれだけの兵を韓国に派遣するつもりか」
と、伊藤。
「一個旅団です」
川上はさりげなく答えた。伊藤はその程度ですら不満であった。多すぎるな、と言った。
「いいかね、もう少し兵数を少なくするのだ」
「閣下、おことばですが」
川上は、まゆをひそめた。
「それについては請合いかねます」
伊藤の命令には従わぬと言う。
首相に対し、参謀次長が胸を張ってこのように言うについては法的根拠があった。伊藤が作った憲法はプロシャ憲法を真似したものであり、それによれば天皇は陸海軍を統率するという一項があり、いわゆる統帥権とうすいけん
は首相に属していない。作戦は首相の権限外なのである。このことは後になると日本の国家運営の重大課題になってゆくのだが、そういう憲法を作ってしまった伊藤は、はるかな後年、軍部がこの条項をたてに日本の政治の首を締め上げてしまうに到ろうとは思わなかったであろう。
ただしこの場合の伊藤と川上の会話は、それほど深刻ではない。川上は維新創業の元勲として伊藤を尊敬していたし、それに川上自身、昭和期の軍人のようにこの国の政治を壟断ろうだん
してしまおいという野心は全く無かった。
「出兵するかどうかについては閣議がそれを決めますし、閣下ご自身それを裁断なさいました。しかし出兵と決まったあとは参謀総長の責任であります。出兵の兵数は、われわれにお任せ下さい」
「憲法だな」
伊藤はにがい顔で言った。彼自身がそれを作った以上、なんとも言えない。
すぐさま人事が決定された。
朝鮮に派遣される混成旅団の旅団長は、少将大島義昌ということになった。それを補佐する参謀は、中佐福島安正と少佐上原勇作の二人である。
──
あの二人はあぶない。
と、陸軍大臣大山巌は思った。陸軍省を主管する陸軍大臣は内閣の一員であり、閣議に制約されているが、参謀長とその参謀本部は天皇に属している。このため自由な行動をとることを大山はおそれた。こにため、この両人の東京出発にあたって大山は厳重な訓示をおこなっている。訓示の要点は、
「アジアを西洋の侵略から守っている者は日本と清国である。もしこの両国が戦うことになれば西洋の列強が漁夫ぎょふ
の利を占め、ついには両国の大害になり、アジアの命脈は回復し難きにおち入る。されば絶対に戦争を誘発する行動は取るな」
ということであった。しかし参謀次長の川上操六はこれとはまったく別の内訓を彼らに与えた。
|