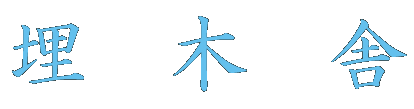落第と退学については、子規の保護者である陸羯南に対し、まっさきに報告に行った。
羯南はこういうことについてすら優しかった。
「いいんだよ」
と、津軽なまりで言った。
「いいのさ」
羯南は子規よりも自分をなぐさめるように言った。羯南は親友の加藤恒忠から子規をあずかり、子規の東京遊学中のことについては責任を持たされている。その子規が落第して退学したとあれば、フランスに行っている加藤に申訳が立たぬように思えるのである。
「いいのさ。加藤に対しては私からも手紙を出しておく。あれはこういうことに驚くような男ではありませんからね」
「先生は、いかがです」
「私も、驚きゃしませんよ」
と、あわらな子規をなぐさめるように、ことさらに顔に力を入れ、うなずいてみせた。
(そりゃそうだろう)
と、子規はひそかに思った。だいたい、叔父の加藤恒忠も陸羯南も司法省法学校の三年生の時にストライキを起こし、退学を命ぜられた。子規の場合よりも不穏ふおん
であり、とても子規を論説出来ない。
その時のストライキで退学させられた者は十六人にのぼった。原敬たかし
、国分青厓せいがん 、福本日南、陸羯南、加藤恒忠だである。ふしぎなことに、退学組の方が、明治大正史にその存在をとどめた。福本日南をのぞいて日本の在野史学は論ぜられないし、国分青厓をのぞいて明治大正の漢詩は論ぜられず、陸羯南をのぞいて明治の言論界は論ぜられず、のちに平民宰相といわれた原敬をのぞいて近代日本の政治は論ぜられないであろう。
「そのかわり、ひどい目にあいましたよ」
と、羯南は言った。退学後の窮迫である。津軽藩の貧乏士族に家に生まれた羯南はいったん弘前ひろさき
に戻ったが、継母とのおりあいも悪く、また食うあてもなく、たまたま創刊したばかりの青森新聞に頼み込んでそこに入ったが、ほどなく辞め、北海道に渡った。当時紋別もんべつ
に製糖所があってそこに勤めたのだが、ここもおもわしくなかった。ついに切り上げて上京したが、職のあてもない。たまたま法学校でフランス語を学んでいたため、その語学力を買われて太政官文書局の翻訳をして暮した。この時期に子規がはじめて上京し、羯南を訪ねたのである。
「私が味わったああいう苦しさは、あれを女に例えれば女郎さえなれずに夜鷹よたか
をして北海道を放浪しているといったものです。決して味わってはなりませんよ」
「しかし、げんに退学しております」
「左様、私の社へおいでなさい」
と、羯南は言った。
羯南はこの当時、明治の新聞界では特異な地歩を占めた
「日本」 の社長になっていた。
「ついでに、私のそばに越して来なさい」
とも、羯南は言ってくれた。子規の生活や病気が心配だったのであろう。
常盤会館宿舎を出た子規は、はじめ駒込追分町三十番地に住んだ。
もとは大名屋敷だったらしいが、今は奥井という人が家主で、庭園もあり、離れ家もある。子規はその離れ家のひとつを借りた。
「きわめ閑静な所で」
と、式は書いている。
「勉強に適している。しかも学課の勉強は出来ないで、俳句と小説との勉強になってしもうた」
そのあとほどなく、根岸に移った。
上根岸八十八番地である。陸羯南がすすめた借家で、羯南の隣家であった。保護者の羯南の隣に住めるというのは、病身のこの落第生にとっては心丈夫であったろう。
隣家の羯南宅から、しばしば読書の声が聞こえて来た。
芭蕉ばしょう
破れて書読む 君の声近し
と、子規は俳句を作って、この新しい環境のあたたかさに浸ひた
っていたようである。このあたりは道幅が狭く、狸たぬき
横丁とか鶯うぐいす 横丁といった横丁が多い。黒塀がつづき、どの家からも古い樹木の枝が道にまでせり出しており、枝の下のどぶは流れが悪く、いつも地面が黒く湿っている。
「いっそ、母さんや妹さんを呼んではどうだろう」
と、羯南は言ってくれた。
子規もその気になり、明治二十五年の夏、松山に帰っている。この当時、妹のお律はもとのひとり身になって正岡家に戻っていた。
母親は松山を離れる事を嫌がったが、かといって子規の病気が気にかかることでもあり、東京移住を決意した。
子規はいったん東京に戻り、この年の十一月九日母と妹を迎えるべく東京を発ち、神戸まで行き、ここで落ち合って十七日に帰京した。
翌日、羯南がやって来て、
「あなたの入社が決定したよ」
と、吉報をもたらした。羯南が社長になっている新聞
「日本」 に入社するという件である。
この件は羯南が社長だから彼の独断でやれそうなものだが、やはり羯南も編集主任には相談する必要があった。編集主任は古島一念こじまいちねんというこの当時の名記者であった。本名は古島一雄といい、但馬たじま
豊岡の人、のち衆議院議員になり、名利に淡白なことで知られたが、昭和二十七年、八十八歳で死んだ。
羯南がはじめ古島に子規の入社のことを相談したとき、
「正岡というのは学歴もちゃんとしているし、文章の才もある」
と言ったが、古島は子規を文学青年と見ていたから乗り気でなく、
「新聞人は学歴も文才もいらない。新聞というものに適格の人でなければならない」
と、その持論を述べた。しかし論説一点ばりの
「日本」 に短歌や俳句の入った紀行文などやわらかい欄も必要だろうと古島は思い、そういうところで賛成した。
月給は十五円であった。 |