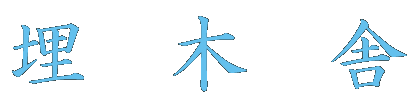子規は東京は去った。
この前後、子規の友人の四、五人も中学を中退して上京した。流行のようであった。東京でのめあては、東京大学予備門に入る事であった。
真之は松山に残されたが、しかしこの若者
(少年というべきか) にも子規と同じ幸運がおとずれた。
「淳」
と、父の久敬が真之を呼んだのは、子規が東京へ去ってからほどなくのことである。
「淳、東京へ行きたくないか」
(なにをお言いじゃ)
と、真之は父親の言い草が気に入らなかった。自分を東京へやってくれる意思もないくせに、話題だけで若い者の気持をなぶるのは年寄りの悪い癖である。
「行きたいが、うちにはお金がありませんじゃろが」
「いや、学資の問題は解決している」
「常盤
会?」
と、真之は身を乗り出した。
「常盤会にあし・・
をいれてくださるのじゃろか」
常盤会というのは、旧松山藩主久松家がつくった育英団体である。
松山藩というのは、維新では 「賊軍」 に準すべき立場におかれ、このままでは薩長が牛耳ぎゅうじ
っている政権の下で虫のように生きてゆかねばならない。この窮状から脱出するには、中央に郷党の秀才を送り出し、政府がたてている最高に学府に学ばせて明治政権に登用してもらい、個々の実力をもって松山の名をあげしめるほかない。そのための学資給与団体が、この常盤会であった。
ちなみに、維新に乗り遅れた中以上の藩のほとんどがこの目的による育英団体を持っていたという点から見れば、日露戦争までの日本というのは諸藩の秀才競争社会であったともいえるであろう。
その常盤会の恩典には、よほどの秀才でなければ浴することが出来ないとされていたが、しかし子規制度の者でも翌年、この会の給費生になり得ているところをみると、やはり多少は情実も伴っていたのかも知れない。子規の年若い叔父の加藤恒忠が外遊に先立って運動しておいたのである。
ところで。
真之の父の久敬は、県の教育官吏であり、国もとにおける常盤会の事務をもとっている。情実をきかせるとすればこれほど有利な立場はない。
が、久敬は怒りだした。
「ばかな」
と言った。おれの立場としてそういうことが出来るか、というのである。
「
あし・・ が常盤会にことをしている以上、お前は入るわけにはいかぬ。常盤会でのうて、兄の信から手紙が来たんじゃ。すぐ上京せい、と」
「
あし・・ が」
真之は、畳の上から両ひざごと飛び上がらせた。真之にはそんな器用な事が出来た。 |