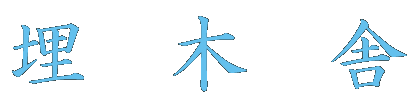この話には、あとがある。
書生は加藤某といったが、根は臆病な男らしい。やにわに右肩をあげた。
「それが、先輩に言う言葉か」
と凄
んでみせたが、病犬のように激しく息をしている。好古はうつむいたまま黙殺した。相手が飛びかかってくれば、死んだ気になって戦ってやるつもりだった。
が、加藤はいなくなった。
好古は手持無沙汰になった。やがて部屋が、暗くなった。部屋の隅へ行って行燈あんどん
に火を入れていると、表で、
── 出て来い。
という声がした。
「はい」
と返事をして好古が外へ出て見ると、闇にそびえるような大きさで人影が立っている。
「ついて来い」
と影が言った。
この旧藩邸には、旧藩時代の道場がまだ残っており、物置になっていた。
そこへ入らされた。大きな影に見えたのはこの書生寮の世話人の某だった。
「おまえ、さっき加藤にさからったそうじゃの。わが・・
とわが・・ 身を偉いものとおもうとるらしい」
「いや、ナンチャ思うとりませんがの」
「いやさ、思うとる」
それほど偉い者なら、どれほど偉いか、ためしてやる、と世話人は言って竹刀しない
を一本好古にわたした。
「撃って来い」
世話人は素手で立ちあがった。好古はなすすべもない。
侍の子でありながら剣術は苦手だった。撃剣をならう年齢がちょうど維新の瓦解期にあたっていた関係上、撃剣どころか家事の手伝いや他家の風呂焚きでいそがしかった。
「撃って来い」
仕方がなかった。振りかぶって、撃った。むこうは、わずかにかwした。さらに撃ちかかって行ったが、むこうは素早く位置をかえてしまう。
いつのまにか、加藤某も入って来て、薄笑いをうかべ、
「その程度の腕でわしに刃むかおうとしたのか」
と、戸口から言った。好古はつい逆上し、声をあげて世話人に撃ちかかって行ったときその手もとに飛び込まれてしまい、利き
き腕うで をねじあげられ、竹刀を奪われた上、足をはらわれて大きく転倒した。そのはずみに陶製の大火鉢で頭を打ち、気を失った。
朝、この物置で目がさめた、血がひいたままで流れてこびりついており、右肩、左腕、首筋を撃たれたらしく、動かそうとすると激しく痛んだ。
(なるほど世間は)
と思った。えらいところじゃ、と思い、そう思いつつ起き上がり、やっと脚をまげてあぐらをかいた。恨んでやろうかと思ったが、性分しょうぶん
なのか、ふしぎにそういう感情が起これない。
とにかくこの体で、今から学校に出頭し、願書を出さなければならなかった。しかし歩けるだろうか。 |