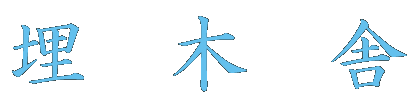「どうだ、今晩でもわしの家に来ぬか」
と、和久正辰は、授業が終わって休憩室に引き上げて来た好古の言った
「酒を飲ませる」
その言葉に思わずのど
が動いたのを、好古は愧は じた。幸い和久正辰は気づかず、待っているから早く来いよ、と大声で言い捨てて出て行った。
──
ばかぁ。
と、好古はわが頭をなぐった。人間、ひとの言葉が生理に反応するなど恥ずべき事ではないか。
(どうも、伊予者は人間が柔やわ
だ)
と、ひとからそう言われる。サッチョウのやつらに伍ご
してゆくにはよほど人間をつくりかえぬといかぬと好古はちかごろ思っている。もっとも幸か不幸か好古はまだ薩長の人間と競争場裡きょうそうじょうりに立った事はなかったが。
夕刻、下宿を出た。
寒い。木綿もめん
の粗末な羽織を着ていた。羽織はおとなになったしるしのようなものだからと思い、古着を一枚買ったのだが、裏がよほどいたんでいたらしく、三日着るとすだれのように破れはじめた。
好古には、金がない。
いや、あるにはある。ななんといっても月給三十円で、それだけもあれば七、八円で玄関つきの屋敷を借りてたとえ家族持になってもゆっくり養えるのである。ところが、好古は下宿代と書籍代をさしひいて毎月松山にいくらか送り、残痕は下宿の夫人にあずかってもらっている。積み立てて将来の学資にするつもりだった。
和久正辰の屋敷に行くと、玄関まで夫人が出迎えてくれて、ぬいだ履物はきもの
までそろえてくれた。
本来なら、好古はとびあがって恐縮せねばならぬところであろう。なぜならば夫人の実家は徒士組の組頭二百石という、秋山家にとって先祖以来代々の上司の家なのである。
「履物は、あし・・
がそろえますけん」
と、好古がゆるゆる手をのばしたときにはもうそろえられてしまっている。
「好古さんは男ですからね」
男だから手をくだしてそろえなくてもいいのか、そこのところがあいまいだが、とにかく口より体が機敏に動いているという、小柄できびきびした婦人だった。
正辰の書斎で、ご馳走になった。
「耳よりな話、といっていたのは」
と、酒のなかばで、和久正辰が言った。
「官費ただ
の学校があるのさ」
月謝も生活費もただであるだけでなく、師範学校と同様、小づかいまでくれるというのである。
「どこでございます」
「東京だよ」
一期生、二期生はすでに入校している。その募集要綱が全国に配布されるのが遅れ、この学校の一期、二期という開校早々の募集は東京の政府筋に近い者が耳ざとく聞き伝えておうぼした。この名古屋あたりに書類がまわってきたのは、こんどの三期生からだという。
「いったい何という学校でございます」
|