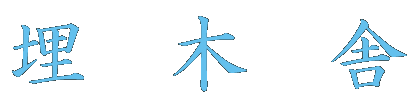名古屋には、和久
正辰という同藩の先輩がいることを、好古は知っている。
(親切なお人じゃ)
と、好古は素朴そぼく
に思っていた。好古が大阪の師範学校にいたとき、なにかの名簿で調べて好古が松山出身であることを知ったらしく、
「名古屋へ来ないか」
と、手紙をくれたのである。和久正辰の手紙は壮士の演舌のように激しく、薩長藩閥が天下をあたかも独占してしまっていることを憤慨し、それにひきかえ伊予松山藩が微々としてふるわぬことをなげき、
──
今後は若い者に待つしかない。
と言い、 「たまたま自分は愛知県の教育界にいる。仕事の余暇に全国七つの師範学校の在校生の出身県を調べたところ、意外にも松山人が大阪の学校にいることを知り、旧藩のため心強く思った。それによってこの手紙を出すのである」
と書いてあった。
(えらいことだ)
と、好古は思った。
おとなどもの藩意識の強さが、である。好古などは十歳の幼さで明治維新を迎えたから、あの時藩が土佐藩に占領管理されたくやしさというものはあわい思い出でしかなくなっている。その後体が成長して世間に目を開いたとき、もはやこの新しい時代に何の抵抗もなく全身で浸ひた
りきっていた。
── 勉強すればご飯が食べられるようになる。
というこの時代の特徴を疑いもなく受け入れ、そのことだけを希望に大阪に出て来た。
いまそれが実証され、月給三十円という高給を保証されつつ名古屋に赴任するのである。
ところが、好古より一世代、二世代年上のひとびとになると、すべての意識が
「藩」 から出発しており、自藩の微弱さを思うとき、薩長が呪のろ
わしく、反面、自藩の不振がなげかわしく、議論がそこにいたると身も世もなくなるほどに昂奮するものらしい。この熱意や競争意識が、いわばこの時代のエネルギーのひとつになって様々に形を変えつつ時勢を沸騰ふっとう
させているのであろう。
名古屋に着いた。
── 県立師範学校はどこですら。
と聞くと、医学校と並んで名古屋における最高学府であるだけにすぐ分かった。その付属小学校が好古の新しい職場だった。
その付属の主事が、旧松山藩士和久正辰なのである。
主事室に入ると、
「よう来た」
と、立ち上がって冷酒をいっぱい、湯呑に満たしてくれた。
「のどが、かわいたろう」
好古は一礼して、湯呑を両手で捧げながら呑んだ。途中でどうやら酒らしいと気づいたが、のどの方が承知をせずにぐびぐび飲み下した。このおだやかな青年はいまだかって酒を飲んだことがなく、これが初めての経験だったが、酒というものがよほど体に適あ
っているらしく、声をあげたいほどうまかった。 |