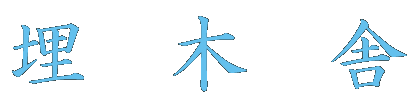大阪行きは、年があらたまった正月になった。明治八年である。
船で行く。
このころ内海には日本人資本による蒸気船がさかんに活動していた。松山の港は、三津浜である。
桟橋
もなかった。ただの海浜で、その波打なみう
ち際ぎわ に小さな伝馬船てんません
が待っているだけである。
「お金を落さんようにな」
と、見送りに来た母のお貞が言ったが、信さんが両親から貰った金は運賃のほかはわずか三円しかない。三円では、大阪に着いて宿をきめて食費を払ってということを勘定すると、十五日ほど食えるのがやっとであろう。
「あし・・
は、三円でええ」
と、この若者は言ったが、このあたりは悲壮を通り越してむしろ滑稽味こっけいみ
を帯びていた。もし小学校の教員の検定試験に合格で出来ぬとなると、国に帰る運賃もなければ、食っても行けず、はじめての大阪で飢えて死ぬしかない。働くといっても維新後大阪は不況つづきで土工の口すらめったにないというのが風説であった。
それにしても秋山家にすれば三円の支出がやっとであったろう。
「小学教員になったら、七円もらえる。やがて返すけんな」
と、信さんは父親の言い、伝馬船に乗った。沖で、親船に乗り換えた。
信さんは古着を仕立て直したカスリの着物に小倉こくら
の袴はかま といういでたちだった。
同行者が、一人いる。
旧松山藩の儒者の子で、近藤元粋げんすい
と言い、これは信さん ── 秋山好古 ── より九つ年上であり、すでに大人である。信さんと同じ目的で大阪へ行く。
「近藤のニイサンはいくら持っとるがの」
と、信さんは船中で聞いた。
「三十円ほどか」
数えて二十六歳になる近藤元粋は言った。信さんは目をまるくして、
「ほな、あし・・
の十倍じゃ」
と、言った。近藤は苦笑したが、
(いくら小僧でも三円では無理ではないか)
とも思ったりした。
近藤元粋の父は名州めいしゅう
と言い、詩文をもって有名であった。長兄は元修と言い、信さんが生まれた年の安政六年、幕府の最高学府である昌平黌に学び、業を終えたときに維新の瓦解が来た。版籍奉還はんせきほうかんまでは藩の学問所の教諭きょうゆ
をしていたが、藩が県になってからは私塾を開いて城下の子弟を教えている。
その元修の三番目の弟である元粋も家中では知られた秀才だったが、藩がなくなってしまった以上、志をのばす場所がなく、道を小学校教員の世界に求めようとしていた。
近藤元粋はのち南州と号し、大阪で猶興ゆうこう
書院という学塾をおこし、在野の漢学者として活躍した。
「すべて薩長の世じゃけん」
と、元粋は船中でしきりにそれを言った。
「伊予者などは学問のほかは頭をあげられぬ。学問の中まで薩長は入ってくるまい」
この近藤のニイサンというのは、ちゃんと紋の入った羽織を着ていた。船に乗るまではまげ・・
を結ゆ っていたが、大阪で試験を受ける都合つごう
から流行のザンギリ頭にかわっている。 |