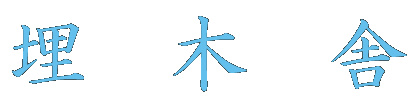家康が広間を出ると、随行して来た本多佐渡が案じ顔に寄って来た。
「帰るぞ佐渡、「馬の用意を」
「かしこまりました」
一礼してかたわらの鳥居新太郎を眼顔で馬の用意に走らせてから、
「関白殿下の、ご機嫌はいかがで?」
と、声をおとした。
「決まったぞ佐渡、小田原の処分は」
しかし佐渡はそれに格別注意をひかれた様子はなかった。あるいは家康と秀吉の会見している間に彼は彼独特の諜報網で秀吉の近侍から何か聞きだしているのかも知れない。そんな点では天才的な佐渡なのだ。
佐渡はいっそう声をおとして、
「関八州に、甲斐をおつけ下さる件、ご交渉なされましたか」
家康は軽く首を振った。
「いま、その時機ではないようじゃ」
「これはまたお気の弱い。事が決着いたしてからでは、ぐっと殿下の方がお強くなられる」
家康はそれには答えず、
「氏直は助命のうえ高野山へおもむくことになった。寛大ななされ方じゃ」
「はい、捨て扶持一万石ほど・・・・これは、ご当家の新領から削り出させられるということで」
「不服そうじゃのそちは」
「足りませぬのでなあ」
「何が?」
「新領の、ご一族やご譜代への割り振りが・・・でござりまする」
家康はキラリと佐渡を振り返って、
「たしなめよ。この地を召し上げられて切腹する人もあるのじゃ」
そしてそのまま大玄関へ出て行くと、曳かせた馬には乗らずに、つかつかと大庭の端へ立って早川口から上方口へずらりと並んだ敵味方の陣屋を見おろしていた。
はげしい夏の陽射しの下で、海から吹き上げる風になびいている旗差し物と緑の重なりが、絵を見るような鮮やかさだった。
その鮮やかな風景の底で、しかし、敵と味方の感慨には雲泥のひらきがあろう。
一方は恩賞の胸算用
に心をときめかせ、一方は身の行く末を案じて生きた心地もないのだろう。
本多佐渡も家康に寄り添うようにして立っていたが、これもしばらくは口を開かなかった。
「佐渡」
「はい」
「これだけの天嶮に城を築いて、ほとんど戦らしい戦もせずに滅んでゆく。おかしなものよのう」
「心からでござりまする。まこと、わが身の心ほど恐ろしい敵はござりませぬ」
「氏直はのう、滝川の陣屋へ両三日止めおかれる」
「はい、そのようでござりまする」
「わしから婿へ最後の贈りものじゃ。今まで各地の戦で戦功あった者には、今後いずれへ奉公あるも苦しゅうない旨、印判状を渡してやるがよいと、滝川を通じて氏直に申してやれ」
「かしこまりました。そして、その印判状持参の者は、ご当家においてお召し抱え・・・・」
「そうじゃ、主家へ忠義だった者はのう、拾うてやらねば人の道が正されぬわ」
家康はそう言うと、もう一度小手をかざして敵陣を見やった。
陣屋と陣屋の間を往復する人の姿が、蟻のように、はかなく小さく、あわただしく見えるのが切
なかった。 |