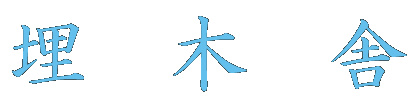光悦はきゅっと唇を噛んだまま、全身を固くして自分の膝を睨みだした。
どうやら利休は、彼が考えているほど浅いところで妄想している人間ではなかったらしい。
それにしても、秀吉と関白とを別々に考えよとはおかしな詭弁
のように思える。
「もう一言、余計なことを言わして貰おうかの光悦どの」
「・・・・・・」
「こなたも、そしてこの利休も、もし武将になろうとすればなれた者じゃ。武将としては世に出る能力がないゆえ、こなたは書道やら刀剣の目利きをやり、わしは茶の道に入ったというのではない。二十万石、三十万石取りの武将になり、一国半国を治めてみたところで満足できる生まれつきではなかった。それゆえ、こなたは武士の魂を預かる道を、わしはこの茶の道をめざした。よいかの、政治や謀略にはある種の醜さはつきものじゃ。その醜さの許せぬ生まれつき・・・・これが、こなたやわしの持って生まれた業
なのじゃ。この業は関白どころか、一国の国王とも必ずと言ってよいほど衝突しよう。げんにこの利休も、いま、関白のご不興をこうむって、こうして病気を言い立ててお側へ出ずにいるところじゃ。しかしわしは関白を憎まぬ。憎むどころか、こうしてしばらく離れていると、何とも言いようのない面白さと、なつかしさを持ったお方じゃ。言うならば、瑾
だらけの、しかし得難い井戸の茶碗とでも言おうかの・・・・」
「居士!」
「わかりかけたようじゃな。眼に光がよみがえったわ」
「すると居士は、この光悦に、秀吉という茶碗に盛られた茶も、そのまま喫する大きさを持て・・・・と、こういわっしゃりまするか」
「そうげはない」
利休は、ゆっくりと首を振った。
「こなたはこなたで、許せぬぎりぎりの一線があるはず・・・・同じことなのじゃ、利休にもそれはある。それはお互いに曲げまいぞ・・・・しかし、そこまで見きわめずに怒り散らす愚は避けよう」
「ふーむ」
「わかったようじゃの。われらの生命は真をめざし、政治の生命は今日の安居をめざしてゆく。どちらの道が険しいかは、こなたがよく知っているはず・・・・」
光悦はガックリと首を垂れた。
はじめて利休の言葉が、しみじみと、腸
にしみとおって来たのである。
光悦や利休のあり方と、武将や政治家のあり方とが衝突なしに済むはずはなかったのだ。
当然あるはずのものに行き当たり、前後を忘れて怒った自分を、利休は
「若い ──」 と評したので、決して世故に負け、濁りに譲れと言っていたのではないようだった。
「すると、もう一つ・・・・」
「おう、なんなりと訊くがよいぞ」
「この光悦も、このまま病になるべきところ・・・・と、思われまするか」
「そうじゃの、馴れぬこの地で水にあたり・・・・それゆえ京へ戻って療養したいと申し上げてみよ。すると関白は、こなた以上に、こなたの身を案ずるやも知れぬ。関白秀吉とは、そのような妙なお方じゃ。武将としても、政治家としても、器
が大きい」
そこへ弟子たちが湯づけの膳をささげて入って来た。もうすっかり夜であった。 |