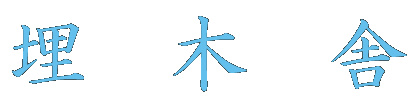利休も光悦も黙って食事を始めた。
(もう、何も言わずともわかったはず・・・・)
利休はそう思って口をつぐんだのだが、光悦の方はそうではなかった。
まだいろいろに、利休の言葉を咀嚼
し直しているのであった。
二人の性格は、年齢の差をのぞけばよく似ていた。どちらも潔癖で負けぎらいで、世の言ういっこく
者であった。
しかし、それだけにどちらも物事の本質を見きわめなければ承知できない純真さを持っている。
光悦は日蓮宗を信じ、利休は禅に参入しながら、どちらも一世の師表でありたいというような、野心に似た覇気
を持っている点までが酷似
していた。
その利休に、光悦は
「若い ──」 と軽くいなされたのだ。これは、相手の言い方が軽ければ軽いほど、手きびしく突き放されたことにもなる。
光悦はいま、その無念さと、性格から来る鋭い反省とを噛み分けているのであった。
居士は、
(秀吉でなくとも、利休や光悦のような生き方をめざす者は必ず時の権力者と衝突するものだ・・・・)
そう言いきって聞かせてくれた。
(そうかも知れない・・・・)
いや、あるいはそれが政治をめざす者と、求真の道をめざす者との宿命的な相違に違いあるまい・・・・そう思いながら、何とも納得できないのはやはり
「若さ ──」 から来る怒りなのであろうか?
居士はここで怒ると秀吉のために自滅させられるぞと警告してくれている。それよりも、病気を言い立てて京へ戻れ・・・・と。
そうすれば、あるいは人間としての秀吉の、もう一つの面を発見して、光悦の心を開かせる原因にもなろう・・・・と忠告してくれているのだ。
(それも、そうかも知れぬ・・・・)
と言って、いつも権力者の前から敗退していて、それでよいのであろうか。祖師日蓮はその敗退をこそ最も戒
むべき卑怯と訓えているのではなかったろうか・・・・?
利休が二ぜん目の飯に口をつけたとき、三菜の蕗
に手をつけていた光悦が、いきなり箸を投げ出して泣き出した。
利休は澄ましていたが、給仕に出ていた弟子はビクッと体を波打たしてひとひざ退った。それほどはげしい光悦の動作であり泣き声であった。
「ヒヒ・・・・」
と、光悦はひきつるように肩を震わせて両鬢
を掻きむしった。
「わしは・・・・わしは・・・・ここまで来ていて、何もなし得ぬ人間だった・・・・」
「そうではない!」
と、利休の声があたりを押えた。
「この次、同じような困難に出会うたとき、こなたは、道のために敢然と死ねるほどの経験をしてのけたのじゃ」
「なに、次には敢然と!・・・・」
「そうじゃ」
利休はそこで低く笑った。
「よいのう、その経験をしてのけたのは、こなた一人ではない。利休もまたおなじ経験をしつつある。楽しいではないか。道のために、真剣に考えられると言うことは・・・・さ、盛りかえて腹をみたして、それからすぐさま、京へ戻る用意にかからっしゃい」
光悦は、もう一度首を垂れ唇を噛んで泣き出した。 |