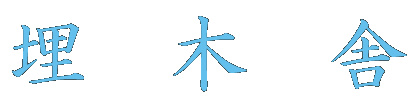利休は光悦の怒りを無視して、弟子の運んで来た風炉
の前に坐った。
燭台を引き寄せて茶器を調べ出すと、さすがに光悦には口をさしはさむ隙を与えない。
まさに 「鎮魂 ──」 の茶であろう。ふくさを捌
く手もとから、目も心も時空
の中に溶け込んで、あるのはただ暮れおちた谷間の静寂だけであった。
茶碗はどうやら、今、戦場にある古田
織部正 の焼かせた
「天正黒 ──」
らしい。
それをそっと光悦にすすめてから利休は言った。
「どうじゃな、わしが、新しい茶碗を高く売りつける、金ばかりが目当ての売茶
翁 じゃという悪口は聞かなんだかな」
「聞いてはいるが今日までは・・・・」
「信じなかった・・・・しかし、これからは信じると言わっしゃるか」
光悦は答える代わりに掌
の中の茶と茶碗を賞味しようとあせっていった。
(若い!) と言われた一言が無性に彼をいら立たせる。果たして自分の怒りは軽率だったのか? それとも相手の世故
の汚れが、こっちの若さを瞞着しようとしているのか・・・・?
それにしても茶の美味
さはまた、何という意地の悪さで彼の味覚を引っかきまわして来るのであろう・・・・
利休はと見ると、もう意地の悪い三白眼
になって、一椀の茶が光悦の内部に、どうした変化をもたらすかと、それをじっと見守っている様子であった。
光悦が茶碗を置くと、利休は言った。
「どうじゃな、心が洗えたかな」
「さ、それは・・・・」
「こなたの知恵などは、どうせ悪知恵じゃ。無にならっしゃれ。それがこなたの言わっしゃる祖師のお心以前に、必ず杖を曳かねばならぬ日暮れの道じゃ」
「ならば、この光悦の考えなど、まだ取るに足らぬと言わっしゃるのか」
「さあ・・・・わしは言わぬ。が、茶は、そうこなたにささやきかけはせなんだかの」
「・・・・・・」
「光悦どの」
「な、なんでござりまする」
「こなたが、どのように逸
っても関白を思いのままには出来ぬものじゃ。もししてみても、それで終わりなどというものではない。一人の関白の次にまた別の関白が、その次にはまた別な・・・・と、決してこの世は果てしはない」
「・・・・・」
「それゆえ、祖師日蓮も、三度諌争して通らずば山にこもってあとの工夫
をなすべきものと、潔
く身延山 にこもられた由を聞いている。よいかの、わしが三両金よりは五両金下さるお方に手さすびの品を贈る・・・・そう申したのは、その後の工夫に嘱
するものじゃ」
「な・・・・な、なんと言わっしゃいまする!」
「いかに手すさびとは言え、この小品の中にはの、わしの今日までに辿り来たった根性のほどが刻み込まれている。これをわが身から手放すのじゃ。五十金、百金にも替えがたい・・・・いや、わしの側からの惜しみはよそう。譲られた人々が、この価値を見出す端緒
はの、残念ながら金高にかかって来るのじゃ。大金を出した品とわかれば必ずこれを珍重して、後々までもその美の価値を見てくれよう・・・・関白の代にも、その次の次の関白の代にものう」
そう言うと、いつか利休は眼をうるまして、そっと手作りの茶さじに頬を寄せていた。 |