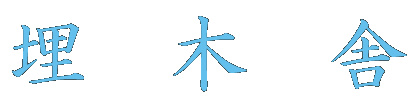寧々はさり気なく笑って頭を下げてから、
「うかがいたいことがござりまする」
自分で燭台を二人の間へ近づけて坐った。
今宵だけはどんな場合にも笑いを消すまい・・・・そう考えていながら、ともすれば頬のあたりが引きつりそうで気にかかった。
「うかがいたいこと・・・・この部屋の絵を描いた絵師の名か。これはな、こんど、日本一の称号を許してやった狩野永徳じゃ」
秀吉は敏感に寧々の意図
を感じ取って、ずるい目をして最初から煙幕
を張って来る。
「日本一にもいろいろござりまするようで」
「そうじゃ、茶では利休、茶碗では長次郎
に許してやった。刀の目ききでは本阿弥
光二 、これから、謡いも舞いも日本一を許してやる。そうなると、もろもろの職人や芸人どもの中にパッと一度に花が咲くぞ。みなそれぞれ技を競うて務めるかのの」
「女子では、いいえ、女子に数を持つ日本一は?」
「な、なに!?」
「側室の数での、日本一はどなたでござりましょうかなあ」
「あああそのことか、それならば家康かも知れぬの」
「それは残念な、なぜまた殿下が日本一におなりになされませぬ」
おだやかに言われて秀吉は、眼をクリクリさせた。ただならぬ空気は、はじめから感じ取っていたらしいが、笑いながら、これほど鋭く肉薄されようとは思っていなかったらしい。
「ハハ・・・・何か聞いたのお許
は」
「何を・・・・でござりまする一向に」
「ハハ・・・・つまらぬ噂を立てるものでの。わしが、それ、利休の娘のお吟
とか申すを、側女 に望んだとか望まぬとか・・・・」
「ホホ・・・・居士
の娘をなあ」
「そうじゃ。しかし、これには訳がある。近ごろ利休がのう、時々わしにさからいおる。わしには侘びはわかってもさび
はわからぬなどと不遜なことを申すのじゃ。話はの、何でもない、長次郎が茶碗のことじゃ。こなたも知ってのとおり、この聚楽へやがて主上をお招きしてその折り、長次郎の茶碗もお目にかける予定なのじゃ。ところが利休はそのおり黒い茶碗でなければならぬとこう申す。わしは黒は好かぬ。趣
がない。それより赤がよいと申したところ、満座の中でわしを叱りおった。赤は雑ぱくを表す色ゆえ、伝統と気品を重んずるころでなければならぬもの、茶や茶碗のことは利休にお任せなされとなあ」
「ホホ・・・・」
「笑うな。そこでわしに向かってな、利休は思い上がっている。あれは心に謀叛
の兆 しがある・・・・などと申すものがあるゆえ、冗談を申したのだ。そのような心があるかないかは、あれの娘のお吟を奉公に出せと申してみればわかることじゃとな。するとそれが差し出せと言ったようにもう評判になっておる。どうせそのような話をして歩くものは宗安
か曾呂利 であろう」
「殿下」
「なんじゃ。鹿爪らしい顔をして」
「居士の娘のことはわかりました。阿茶々の方はどうなさりまする。これも口の軽い人たちの、あらぬ噂と存じまするが・・・・」 |