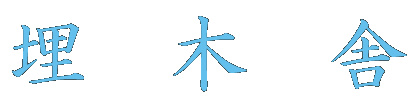「恐れながら、その儀はひとえに殿下の思し召しによること・・・・この有楽に意見などあろうはずはござりませぬ」
有楽は、もう完全に寧々に屈服した形であった。
「ただ、殿下からは、とにかく、こなての手もとへ預かりおくよう、そのうえで改めて指図しようと仰せをこうむっておりまする」
「とにかく、こなたのお手のもとへのう」
「はい、殿下にもまだご思案がつきませぬ様子にて・・・・」
寧々はそこで訊くのをやめた。これだけ手
酷 しく責めておいたら有楽はもはや小細工はなし得まい。有楽の口からハッキリと、懐妊云々
は、彼の才覚と言わせたことで充分だった。
「大儀でした。移転のことで何
かとお忙しかろう。今日のことはわらわも忘れます。こなた様もお気にかけずに、あとの事を取りつくろうてくれますように」
「恐れ入りました。必ず、政所さまご配慮を無にせぬようにいたしまする」
有楽が退ってゆくと、寧々はそのまま考え込んだ。
(これ以上、有楽をいじめてみてもどうなるものでもない・・・・)
問題は有楽が引き起こした者ではなくて、秀吉のやったことなのだ。
(男というものは・・・・?)
いつもは苦笑して済ませたことが、今度だけは何か妙に気にかかった。胸さわぎと言っても通るまい。やはり嫉妬なのかも知れない。
(なぜあのような小娘に・・・・!?)
そう思ってみると、この小娘は、今までの側室たちにないものをたった一つ持っていた。それは寧々に劣らぬ勝ち気さであり、時には身の破滅を意に介
すまいと思われる類のない自我の強さでありわがままさであった。他の側室はどこまでも寧々に一目
おいている。しかし阿茶々の身辺には、寧々でさえ押えきれないある種の妖気
が漂っているような感じであった。
長い間幸福に背を向けて生きて来た、全身にしみついた虚無かもしれない。
(── どうなっても驚かぬ!)
そんな捨て鉢さが、時には平然として寧々ばかりか秀吉にも反抗させそうで気がかりであった。
それに寧々には何としても出生のひけ目
がある。信長の姪であり、浅井
長政 の姫であり、柴田
勝家 の養い子・・・・と並べて来ると、いずれも寧々の生い立ちとは比較にならぬ家格であった。
寧々はしだいに、この聚楽第が恐ろしいものに思われだした。
(ここで、あの阿茶々と一緒に住む・・・・)
それはずっと幸福に恵まれつづけて来た寧々の生活に、そろそろ暗い影のめぐって来る前兆
ではなかろうかと・・・・
寧々がその事で秀吉に相対したのは、京童
の眼をうばう財宝が、淀から船上げされて、すっかり聚楽第へ運び込まれた十八日の夜であった。
秀吉は上機嫌で寧々の居間へやって来ると、
「どうじゃな、お気に召しましたかなこの奥の普請
は」
眼を細めて、寧々の前へあぐらをかいた。 |