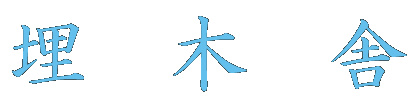有楽とあれば、茶々姫のことかも知れぬ・・・・そう思うと、秀吉は何となく姿勢を改め、柄
にもなくほのかに頬へ血の色を見せて待つ気になった。
折が折りだけに、若い茶々姫との情事は、
(まだわしにも青春があったぞ!)
そんな心の弾
みを伝える。
「有楽か、ずっとこれへ」
「はい、殿下にはいつに変わらぬ・・・・」
「でもあるまい、変わり果てたぞわしはもう」
「何を仰せやら、いよいよ血色もよろしく、お目の輝きも増しましたようで」
「嬉しがらせを申すな。茶々は変わりあるまいの。上洛の準備は終わったか」
「実は、その事で・・・・」
「なに、茶々がことでか、それとも上洛の準備のことで火」
「その、双方でござりまする」
有楽は、ぐっと胸をそらすようにしておだやかに頬笑
んだ。
秀吉は何となくひやりとした。
北の政所から心に痛い一針を打ち込まれたあとで、茶々からまた何か言われるのはやり切れなかった。
北の政所はどこまでも
「妻の勤め」 という説教めいた立場で押して来たが、茶々の方はその反対だった。
人も心を憎いほどに見抜いていて、感情の隙
を狙って子供らしいわがままさの矢を射かける。
こちらが心に余裕のあるときにはこの上なく面白い駄々っ子だったが、その相手をしていられないときには持て余す玩具であった。相手を自分の方へねじ向けなければ承知しない自我の強さをもって立ち向って来るからだった。
「茶々がまた、何ぞ申したのか」
「はい、聚楽第へお移りの行列には加わりとうない。ご遠慮申したいと、こう言いますので」
秀吉は眉根を寄せて舌打ちした。
「ならぬと言え!」
「はい、それはもはや決定しましたことゆえ、ご無理であろうと申しましたがききいれませぬ」
「聞き入れぬではない!
きき入れさせなされ。何じゃお許
がついていて」
「と、仰せられまするが、殿下もご承知のようにあのお気性ゆえ、いったん言い出すと有楽の手には負えませぬ」
「それで、わしに何をせよと言わるるのじゃ」
「恐れながら、殿下おみずからお説き伏せ下さりますよう」
「わしに説けと?」
「はい、有楽に手には、なかなかもって負えませぬので」
有楽はそう言うと、茶々の気性は知っているではないか・・・・と、いう風に、自分から視線をそらして膝の白扇
をもてあそびだした。
秀吉のもっとも嫌な、取り澄ました有楽の姿勢の一つであった。
利休も時々こんな一面を見せたが、これは心で秀吉を軽んじている証拠らしかった。
「有楽」
「はい」
「この期
に及んでわがままは許さぬ。そう申せ。それでよいのじゃ」
「と、仰せられまするが、姫の方にも申し分はありまするようで」
有楽はゆっくりと、
「あるいは、姫は懐妊
しているやも・・・・そうなりますると、輿
の旅は、身の毒かと・・・・」 |