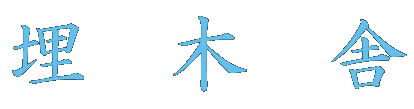「それをうかごうておいて、茶屋は茶屋らしゅう、手を打ってみるつもりでござりまするが」
茶屋は、数正の顔を見ているに忍びなくなって、そっと座を立つ気配を示した。
「そうか、そう言われるに違いない!
そのような気がして参った」
数正はもう一度虚空を見つめてつぶやいて、
「このまま戻られるか」
「はい、ご事情をうけたまわれば、無理にお宿も願えませぬ。ちょっとご挨拶だけ申し上げ、城下へ旅籠
を求めることのいたしまする」
「茶屋どの」
「はい」
「城を出て行くときにご用心なさるがよい。こなたが考えているよりも、ずっとみなの憤
りははげしいものじゃ」
「お心も知らず、三河者の欠点でござりまするなあ」
「いや、この単純さ、硬骨さはまた得難い美点での、彼らがこの数正を腰抜けと罵り、歯痒いと立ち騒ぐあいだは、ご主君もご安泰であろうゆえ」
「つくづく感じ入りました。まこよお家の柱石にござりまする。では、くれぐれもお体をおいといなされて、ご大任を果たされまするよう」
「かたじけない。ではこなたも・・・・」
そこで数正は手を叩いて、さっきの若侍を呼んだ。
「客人が戻られる。玄関までお送り申せ」
「かしこまりました」
茶屋はもう数正には声をかけず、うやうやしく一礼してそのまま廊下へ出ていきながら、
(ふしぎな奉公もあるものだ・・・・)
と、しみじみ思った。
秀吉という、ひろい幅の人間は、家人の人を計る尺度をはるかに超えている。
それだけに、秀吉の言行すべてが、素朴な三河武士には、信じがたい詐術や謀略に見えるらしかった。
あるいは大将として軽薄で気障
で移り気で鼻持ちならぬのかも知れない。それにしても、その秀吉のもとへ使者に立ち、人質のことを伝えて戻ったからと言って、数正のもとへ出入りする者にまで眼を光らしているのだとは恐れ入った偏狭
さと言うよりない。
(ことによると石川どのも、少し神経質になりすぎているのではあるまいか・・・・)
そんな事を考えながら城門を伝馬口の方へ出て、従えている二人の手代に話しかけようとして振り返ったときであった。
「待て!」
濠
沿 いの松並木の下から面を包んだ二人の武士が出て来て、茶屋の前へ立ちふさがった。
もうすっかり夜になって、あたりは男女の別を見分けるのがようようくらいの暗さであった。
「はい、何のご用でござりましょう」
茶屋は内心呆れながら足をとめた。
(なるほど見張っていたぞ。これはこれは)
「その方の名は何と言うぞ」
「茶屋と申しまするが何か・・・・?」
「茶屋と申すと松本清延どのじゃな」
「さようでござりまする。この間まではそう申して武士でござりました・・・・しかし今では、お暇をいただき、呉服商人の茶屋でござりまする」
言いながら四郎次郎は、相手が刀の鯉口
を切っているのにいよいよ呆れた。 |