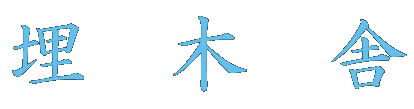茶屋四郎次郎は落ちだした雨をたしかめると、笠を傾けて足を早めた。
いま、石川数正を訪ねてみても、言う事は何もなかった。すでに平和の条件は決まっていて、茶屋の意見をさしはさむ余地などは全くない。
それでいて岡崎を素通り出来ないのはなぜであろうか?
数正の苦しい立場を、ほんとうに知っているのは、家康と自分だけ・・・・いや、あるいはもう一人、本多作左衛門が知っているのかどうか・・・・そう思うだけで黙って数正の前に立ってやりたい一心からだった。
(もし数正が、自分の前で愚痴のひとつも洩らしてくれたら・・・・)
といって、ただ手を取って泣くことぐらいしかできないのだが、それでいて、やっぱり訪ねずにいられなかった。
もともとこんどの戦は、はじめから複雑をきわめた奇怪な戦であった。
勝ってならず、負くれば身の破滅。
それを胸に包んで長久手の一戦に大勝すると、家康方の家中の主張ははっきりと二つに割れた。
というよりも家康と数正を除いて、主戦論一つに凝
り固まってしまったと言ってよい。
(秀吉怖るに足らず!)
もともと剽悍
で単純な三河武士だった。秀吉のひるむ隙に追い討ちを掛けて、一挙に息の根を止めるか止められるかというように、決戦を望んでゆくのは当然であった。
家康が今は、秀吉を討つべき時ではないと説けば説くほど彼らはいきまいた。他意があるわけではない。家康が、自分たちを労わるあまり、大事なときに逡巡する・・・・それでは済まぬと律儀に考えてのことでさえあった。
したがって家康以外に彼らのこうした強硬な主戦論の前に立つのは数正ひとりであった。本多正信などが口を出しても相手にせず、
「──
主君を気 後
れさせているのは数正じゃ」
「── そうじゃ、数正には秀吉の手が及んでいる」
「── それに相違ない。秀吉のもとへ使いして、ばかされて戻って来たのじゃ」
そうした人々を押えて、とにかく家康は、徹頭
徹尾 秀吉との決戦を避けた。
秀吉もまた、長久手から楽田に引き揚げると、本陣を小松寺山にすすめて、いかにもすぐに攻めかかりそうな気配を見せたまま対峙
戦に入った。
あとで伝え聞くところによれば、小松寺山の本陣で秀吉は碁ばかり打っていたという。
「── 敵の様子が変わりましたが」
前線からの注進が届くと、振り返りもせずに、
「──
向こうが出て来れば戦うぞ。出て来ればな・・・・」
そう答えて、家康の方から攻めかかって来ないことをよく知っていたという。
(そのために敵味方とも、どれだけ多くの生命を捨てずに済んだことか・・・・)
むろんその間、家康の旨を含んで石川数正が、秀吉と連絡していたからのことであったが・・・・
茶屋四郎次郎は岡崎の城下へ入るとまた思い出したように吐息をして、そのころの蒼ざめた緊張しきった数正の顔を瞼
に描いた。
全く、一歩誤れば、どんな破綻
に逢着するか分らない、危うい数正の駆け引きだった・・・・ |