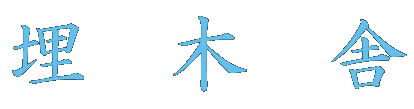勝入はしばらく呼吸をつめて元助を睨
んでいた。まだ怒りの渦
は胸にあったが、いあまそれを元助に見せてはならぬという自制もあった。
冷静に聞いていたら、元助の言葉には一理も二理もあるような気がする。
たしかに秀吉は負けを知らぬゆえ、他人には冷酷なところがあった。家康の戦上手は充分に知っていたし、先陣して来たわが勢が、そうやすやすと勝てるとは思っていなかった。
それにしても、元助が言うような、放火までしてわざわざ局面を悪くしてゆく必要がどこにあろう。
「納得できぬ」
しばらくして勝入は吐き出すように、
「放火の得は、味方の心を引き緊
める。ただそれだけのためか元助」
「これはしたり・・・・敵を強くするのじゃ。わしは・・・・」
「なに、敵を強くする。元助! 敵が強いゆえ、その方は心を砕いているのではないのか」
「強い上にも強くするのじゃ!」
と、元助は言い返した。
「そして、われらが手ではどうにもならぬ・・・・と、これを筑前どのに引き渡してやるのじゃ。さすれば筑前どのは、はじめて、高慢の鼻を折って自省するわい」
「高慢の鼻・・・・」
「さよう。この事は、筑前どのが天下を取る人ならばなおさらのこと、一度は骨身にしみて知らせておくべきことじゃ。そのうえで勝ったら、はじめて勝入、ようやってくれたと、言葉と肚がひとつになる。それを体験せずに勝ったら、褒められても口先ばかりのカラ褒めじゃ」
「ウーム」
と、勝入はうなった。
年齢の差というものは恐ろしい。
そう言えば、勝入の時代の人間にはどこかに気のいい甘さがあった。おだてられると、おだてていると分っていながらそれに乗る、小児のようなところが・・・・
ところが元助の計算はもっと人が悪くて、きびしく急所を突いている。
敵を強くさせておいて、ほんとうに筑前を困らせ、それで自分の骨折りも分らせて行こうとは、何という油断のならぬ算盤
高さであろうか。
「では、その方は、筑前どのの援軍がやって来るまで、徳川には勝たぬというのか」
「また始まった・・・・」
元助は傍若
無人 に舌打ちした。
「援軍の来ないうちに勝てるような敵ではない。それより、あまり安易
に勝利などを考えず、我が家の将来をぐんと深くご思案あるよう、そのために元助の首を打たれてもよいと考えて火を放った・・・・と、こう申し上げているのがお分かりないのか」
勝入はまた黙った。
こんどは前よりも腹立ちが減っている。
(なるほど、そこに元助のいら立ちがあったのか。そう言えば、わしは少し甘かったかも知れぬ)
「では、万一筑前どのが放火のことで、われらを責められたときには何というのじゃ」
「あの、逆賊の高札を見せてやるのだ。あれを読んだ土民どもが手きびしく敵対するゆえやむなく焼いたと言えばよい。あの高札とて、まんざら嘘ではない。事実は事実と、筑前どのにも知らせてやる必要がある」
元助はひびきのものに応ずるように答えていった。
|