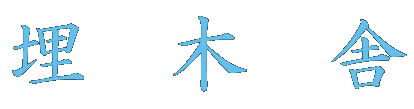勝入はピクリと肩を動かして、
「分った!」
と、低く言った。
「分ったゆえ、退って休め」
語尾がかすかに震えているのは分ったというよりも恐ろしいからであった。
(何を言い出すかわからぬ奴!)
弟の輝政
はまだ二十一歳だったが、これほど激しくはない。こんども、勝入の言うことには、充分、父と子の距離をおいて従って来ている。しかし、二十六歳の元助は平素は無口でありながら、言い出すと何もかも一刀両断と言った論法でやって来る。
高札の文面もまんざら嘘ではないと言われると、秀吉だけではなく、勝入もまた胸を刺される想いがするのだが、これがもし秀吉の耳に入ったらどうする気なのか。
信長の乳母の子に産まれて、信長とともに育った勝入だった。父の紀伊守
恒利 以来織田家に仕えて、その関係は元助ですでに三代にわたっている。
かって勝三郎時代に、信長の弟武蔵守
信行 を手にかけたのも彼であったが、そのときと同じ後味わるい不快さが、実はこんどもなくはなかった。
山崎の合戦に明智の武将、松田太郎左衛門や、斎藤
内臓介 の軍勢を駆け散らしているときのような爽快
さは、敵が信長の子の信雄だと思うだけで、ありようがなかったのだ。
その急所を、わが子の元助に剔
られた気がする。と言って、みずから天下に号令できるほどの実力を持たない以上、勝つと目される方に味方して、とにかく生き残ることを考えるよりほかにないのが今の大名の運命ではなかったか。
(やむを得ぬではないか・・・・)
そう考えたあとで、また腹立たしくなって来たのは、自分に子供がなかったら、果たして秀吉に味方したであろうかと・・・・ふっと考えたからであった。
勝入には勝九朗元助、三左衛門輝政、藤三郎
長吉 、橘
左衛 門
長政 のほかに四人の女子がある。それらの子たちの将来を、考えまいとしても考えさせられるのが人も子の親であった。
勝入はあわてて首を振って妄想
をふり払った。子供がなければ、信雄や家康の側に立って、あの高札を彼の手で立てていたかも知れないと思うことは、何ともやり切れないことであった。
眼の前にはもう元助はいなかった。あたりはすっかり明るくなり、家老の伊木忠次ひとりが、じっと自分に視線を向けていた。
「忠次」
「はい」
「元助は恐ろしいことを申す奴だの」
「お怒りなされずに済んで何よりに存じます」
「わしはあれの申すことを聞いているうちに妙な気持ちになって来た」
「妙な気持ち・・・・と仰せられると」
「もともと信雄どのは憎くはなかった。が、家康もまた憎めぬような・・・・妙な気持ちじゃ」
忠次は答える代わりに、消えかけたかがり火に黙って柴を添えだした。
「わしはここらで討ち死にしたがよいかも知れぬ」
「何と仰せられます」
「いや、冗談じゃ。これは冗談じゃが・・・・さて」
すっと床几を立って、しかし勝入は自分が何のために立ち上がったのか、それがよく分らなかった。
気がつくと、小鳥のさえずりががじけるように聞こえだしている。
|