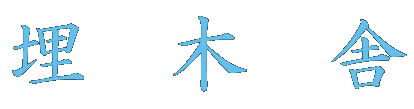(怒ってはならぬ!)
と勝入は自分を押えた。勝入と秀吉の間にある友情は元助にはもう分らないのかも知れない。
それが分らなければ元助の危惧は、父を想い、わが家を想う心のあらわれで、少しも責めるに当たらない事なのだ。
が、それにしても、放火してのけた意味は納得
できなかった。
(そうすることで、いったい何の利益があるというのか・・・・?)
「忠次・・・・」
「はい」
「とにかく元助を呼んでくれ。いや、わしは怒らぬ。わしは元助の考え方を訊きたいのじゃ。わしが筑前どのを見る眼は、あるいは甘いかも知れぬ。が、腑におあちかねるところもある。怒らぬゆえ呼んでくれ」
伊木忠次はしばらく考えていたが、
「ではお呼びいたしましょう」
うなずいて出て行って、すぐに元助を連れて来た。元助は前よりも一層きびしい無表情さで、入って来ると立ったままで父に言った。
「お呼びだそうで」
「立っておらずに掛けなされ」
元助はしかし、床几へかけずその場へ大きく胡坐していった。
「火を放ったのはその方か」
「分っていながら、父上は、ほかの者をお斬りなされた」
「それがその方には不服なのだな」
「不服とは申しませぬが、元助とて考えあってした事でござります」
「その考えを申してみよ。火を放って、われらに何ほどの得があるのだ」
「父上は、こんどの敵を、光秀や柴田修理
の場合と同じに考えておいでなさる」
光秀や修理より弱いとは思うておらぬが、強いと思う心は戦に禁物
じゃ。それを臆病風とわれらは言うぞ」
「これはしたり、われらが軍略では、敵の強さを知ることは、臆病風ではなくて、用意のもとでござりまする。今まではいつも筑前どのの位攻
めで勝たれた。しかし今度はそうは行かぬ。しかも、筑前どのもまた敵を甘く見てござる」
「筑前どのが甘く見ていたら、その方意見を具申
したらよいではないか。火を放って土民の心を失う必要がどこにあるのだ」
勝入は冷静に理詰めでいったつもりであったが、元助は、それだから話にならぬと言う風に頭を振った。
「こちらから意見を上申して訊き入れる筑前どのと思
されまするか。それこそかえって鼻の先で笑われて、すぐにも撃破せよなどと仰せられる。そうなったら、池田勢は敵の餌食
じゃ」
「それゆえ火を放ったか・・・・分らぬ。そのような言い方では」
「分らぬお父上じゃ」
「何じゃと元助!」
「わしはお父上に背水
の陣を若かせたいのじゃ。いや、それが事実いまの池田勢のおかれている位置なのじゃ。うしろには負け戦を知らぬ筑前どの、前にはそれ以上に冷ややかな徳川どの、その両者に挟まれて、土民の味方など恃んでいてどうなるものか。四周すべてこれ敵!
その覚悟をうながすためにすすんで火を放った。悪いかお父上・・・・」 |