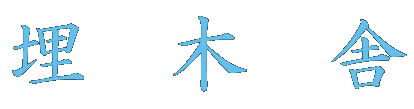勝入はひとしきり、身動きもせずにおのが呼吸を数えていた。
脈拍も息も乱れてはいない。がしだいに気が静まるまでは、疑問がいくつ重なりあっているのかよく分らなかった。
なぜ、元助は秀吉からまで厳禁されている尾張での放火をやってのけたのか?
とっさに伊木忠次が曳
き出して来た武者は何者であったのか?
まこと徳川家の武将榊原康政の家臣であったのかどうか?
(あるいは、元助も放火し、徳川方の者もまた、罪をわれらになすりつけようとして、別に放火していたのではなかろうか・・・・?)
元助が全然身に覚えのないことで、自分を斬れなどと言うはずはなかった。さすれば、元助もまた放火して廻ったことは疑う余地がない。
(そうじゃ、これは忠次を呼んで訊
ねてみねばならぬ・・・・)
が、まずどこから訊
き出すかで、またしばらく勝入は迷った。
「誰ぞある、忠次を呼んで来い」
腰かけたままひと眠りし、眼がさめた態
にしてして近侍を呼んだときには、すでにあたりは夜明けの気配を漂わしはじめていた。
伊木忠次は、やがて勝入が呼びに寄こすのを待ち受けていたと見え、昨夜のままの具足姿でやって来た。
「二人だけで話がある。みなはしばらく来るには及ばぬ」
勝入は中次の到着を告げて来た近侍に言って、はじめてあたりを見廻した。
「忠次、さっきわしが首を討ったは何者じゃ」
伊木忠次は、ひどくムッとした表情で、
「それがしの家臣にござりまする」
「なに、その方の家臣じゃよ!?
では、榊原康政が廻し者だと申したのは・・・・」
そこまで言って勝入は語尾を切った。訊くまでもないことだった。伊木の家臣が康政の廻し者であるがずがない。
「忠次、いったい元助は、何を考えて火などを放ったのであろうかの」
「それを、先に若殿にお訊ねなされば、あもような哀れな者を失わずに済みました。殿ももう少し前後をお考えなされて太刀をお抜き下されませ」
「悪かった!」
勝入はあっさりとあやまった。
「では、あの者に、身代わりになるよう、その方から申し聞かせてくれたのか・・・・悪かった!
遺族などのこと、この勝入も手厚く扱おう」
忠次はまだそれでもムッとした様子で、
「若殿は、殿をご軽率なお方と、私に評されました」
「なに軽率じゃと・・・・」
「人が好すぎるのだとも申しました。羽柴筑前どのを未
だに朋友 と父の方では思うているが、先方ではただの家臣と思うておろう。それゆえ、どのような戦功を立てたからとて、決して美濃、尾張、伊勢、三河など、そっくり下さるはずはない。それどころか、うっかりすると、徳川どのの直前に晒
され、全滅させられるやも計られぬ。その甘さをまず打ち砕いておかなければわが家の末と ── いわば殿への警鐘
のつもりでござりましょう」
勝入は、一瞬、カッと頬を赤くし、しかし、すぐ口を開かなかった。 |