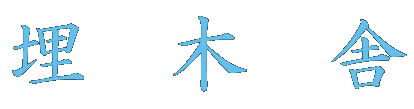作左は本丸の大玄関を出ると、東側に新しく築かれた、俗に作左衛門曲輪
と呼ばれる侍屋敷のわが家へ急いだ。
何かほのぼのとした明るさと、やりきれない切
なさが矛盾 のままで心に渦
を巻いている。
作左衛門自身は、とうに死んだ気で家康に仕えて来ていたのだが、こんどの数正の役目を思うと自分のことのように胸が痛んだ。
石川数正が使いに行くと、秀吉はおそらく、肩を叩き、抱かんばかりにして歓待するに違いない。引出物
も、あの煤け茶壺の何倍かのものをくれるであろうし、徳川家の大忠臣とおだてもするであろう。
そのうえ、きっと、わしの天下になったら、家康に言うて何万石か遣わそうなどと、人間の弱点と本能を衝
きまくって来るに違いない。
それだけならば、決して案ずることはなかった。こちらにがっしりとした土性骨
が徹 っている。
「──
ありがたき仕合わせ」
などと、語呂
を合わせて退出してくればそれで済むのだ。
ところが秀吉は、それだけで、相手を手放す人物ではないこと、信長の死後の行動で、あまりにハッキリとしているのだ。
必ず数正は、われに内応していると、巧妙な宣伝を徳川家の家中にふり撒
いてゆくに違いない。
お互い諜者は放ち合っているので、時には思わぬ秘密が、相手方に洩れてゆくのは避けがたかった。
そうしたときに、
「──あれは数正が知らせてくれたことでの」
そんなことをたびたび言いふらされたり、信長のように偽の手紙などを書かせてあちこちに見せられたりすると、はじまは信じなかった者も、やがては心を動揺させ、いつか警戒から憎悪の眼に変わって、もとの家中に居耐えぬようになっていくのが常であった。
そうなると、秀吉はまた改めて誘いの水を向けて来る。やり切れずにその誘いに応ずると、結局最初から内応していたのと同じ結果になってゆくのだ。
秀吉はそうした術策の鬼才であった。
それをハッキリ見抜いているだけに、作左衛門は、家康に相談された時、誰を推薦
しようかと、しきりに頭を悩ましていたのだった。
そこへ突然、数正の方から、自分が使いしよう、口添えしてくれと、家老の渡辺金内を使者に立て、手紙を持たせて来たのである。
それを見たとき、作左はぐさりと胸へ短刀を突き立てられたような気がした。
これが数正ではなくて、余人であったら、作左はすぐに疑ってみたであろう。
「──こやつのもとまで、もう秀吉の手はのびていたのか・・・・?」
と。もし、立身だけを考える者があったとしたら、いまの秀吉のもとへ使いするのは、絶好の折と言えた。しかし、、作左の知っている数正はそんなことの考えられる男ではなかった。
(これはあれの仏心から出た事らしいぞ・・・・)
それにしても凄
まじい。おそらくこれは秀吉の鬼才に翻弄
されて罠 にわが身を千切られるに違いないのに・・・・
作左は我が家の前に立つと、
「作左どののお帰り」
大声で自分でふれて、のっそりと玄関へ入っていった。
|