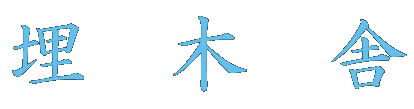筆と硯が持ち出されると、あたりは一瞬にしてシーンとなった。
誰もみな紙一重
向うの 「死 ──」 と改めて対決させられたのに違いない。いや、その対決を怖れて酒を酌み、唄い舞っていたのかも知れない。
お市の方は筆を持ったまま、つと立って廻廊へ出て行った。かすかに風の音が虚空
で鳴っている。眼の下の闇には、敵の焚くががり火が点々として見えていたが、しでにどの櫓
の灯も消えていた。
みんな名残の酒を酌み終わって、最後の眠りについたのであろうか。
勝家も立って来て、深い息をしながら空を見上げ、四方を見おろした。
「みんな休んだらしいの」
お市の方はそれには答えず、遠くで鳴っている鐘の音をとらえていた。
無情か有情か?
空にちりばめられたわずかな星が、人間の営みの儚さを冷たく見おろしているようだった。
「あれが、愛宕
山だな」
勝家がまた南のかがり火を指差して、
「秀吉めが、いまごろ何を考えていくさるか・・・・」
もう自分が、再びその名を口にしないと約束してことは忘れたらしく、
「おお、閑、盃を持てッ」
と、内へ向かってどなった。
それで、またいくつかの顔が出て来て、宴がそのまま廻廊へ移りそうになって来た。
お市の方はいぜんとして勝家に背をむけたまま立っている
「灯
りは持ち出さぬように・・・・」
弥左衛門の言うあとから、
「きゃつらの弾丸
がここまで届くものか」
と勝家がうそぶいた。
お市の方はそのとき、きらりと眼の前を何か黒いものが啼
いてよぎったような気がした。
(ほととぎす・・・・)
ほととぎすが果たして今ごろ、こうした場所を飛ぶのかどうかは考えなかった。
文字おどおり四面
楚歌 のうちに立つ孤城。
せき
として声のない一瞬の悲しみに、もし想いを寄せて近づくものがあるとすれば、それは雲井からおとずれる郭公
に違いないと思った。
お市の方は巻紙をとり直して、すらすらと筆を走らせた。 |
さらでらに 打ちぬるものを 夏の夜の
別れを誘う 郭公かな |
|
「おできになりましたか」
文荷斎が、うやうやしくそれを受け取って読んでゆくと、勝家はコトリと盃をおいて、急にきびしい顔になった。
「文荷斎、筆を」
「はい」
勝家は、もう一度口の中でお市の方の辞世を口ずさみながら、灯りの方へ向き直った。
北国の夜気の冷えが、どうやら勝家の心の乱れに闘いを挑んでゆくらしい。二、三度低くうなるようにして、 |
夏の夜の 夢路
はかなき 跡の名を
雲井にあげよ 山郭公 |
|
| こんどもまた、文荷斎が、ふしぎな抑揚
をつけて、それを読んだ。と、同時に、女たちのすすり泣きが、いっせいに湧きあがった。 |
| 「徳川家康
(九) 著:山岡荘八 発行所:講談社 ヨリ |