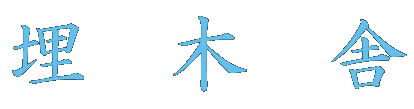「おい来たか。さ、、その方たちもまず呑め。わしが酌する。よいか、酌もしようし、舞いもする。人間五十年・・・・と、右府さまは事あるごとに謡
われたが、四十九歳で亡くなられた。わしはすでに六十二歳、五十年を十二年も生きのびて猿がためにこのような・・・・」
言いかけてまた勝家は大きく笑った。
柴田弥左衛門も小島若狭も、勝家の酔い方を見ておどろいたようだった。
いつもの酒豪が、すでに他愛もなく乱れている。どんなに飲んでもむっつりと四角に構えて、ついぞ酔いを人に見せなかった勝家が・・・・
そのころから、お市の方はだんだん気が滅入
って来た。
(こんなはずはない・・・・)
三人の姫たちを落として、二の丸の広間に戻ったころは、心の隅
まで冬の小川のように澄みきっていたのに・・・・
(殿が悪いのだ。あのように、脂
じんだ執着を見せる殿が・・・・)
はじめには、ほんとうに淡々と悟りきったかに見えた勝家が、だんだん痛ましく哀れな酔いを見せている。
意地も勝気もうわべだけのことせ、内心に泥のような迷いと愚痴
と執着を秘めている。
この分では、やがてお市の方の首に手を廻して泣き出すのではあるまいか。そう思うと、急に自分が怖くなった。
姫たちと離れてまで、共に死のうと考えた勝家が、老醜
だけの愚痴深い男に変わってゆくのを見せ付けられたら、やりきれない悔いが自分を捕らえそうな気がするのだ。
(共に死のうとせまられて、遁げ出すようなことがあったらどうしようか?)
鼓
が鳴りつづけた。側女
たちの手からやがて文荷斎の手に移り、さらに弥左衛門の手に移った。
横笛は若狭が奏
でている。
次々に女たちも舞っていったし、勝家も、あやしい手ぶりで謡曲を誦
しながら舞った。
しかし、その間、お市の方は、なるべくみんなを見ないようにして、じっと、自分の心の底を見つめて来た。
今ごろ姫たちは、どこで、どうしているであろうか・・・・?
彼女たちは母に欺
され、三人だけで落ちていったことをどのように解釈しているのであろうか。
ここでは、みんながこだわりを捨て、最期を飾ろうとあせりながら、かえって息づまる哀れさをひろげている。
人間とは、どうしてこう嘘が好きなのであろうか。悲しいときにはいっそ静かに、その味を噛みしめていてはわるいのであろうか・・・・?
「お方」
と、勝家はまたお市の方に盃を突きつけた。
「さ、もっと飲もう。今宵限りの宴じゃ」
「殿、わらわは辞世
を残しとうござりまする」
「なるほど、辞世をな」
「はい、今宵限りの生命ゆえ、その生命をじっと見つめて逝
きとうござりまする」
「よかろう。分荷斎、筆と硯
を持て」
文荷斎はそのとき、若さの手から笛をとって、しきりに歌口をしめしていたが、
「かしこまりました」
ゆっくりとそれをおいて起ちあがった。
この方が勝家よりずっと落ち着いているように見える。
時刻はすでに九ツ
(午前零
時) 近かった。 |