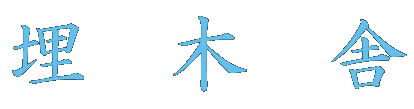「文荷斎、いずれの櫓
へも、酒肴は届いたであろうな」
勝家はときどきかたわらのお市の方を眼を細めて見やりながら杯を重ねた。
「はい。どの櫓へも灯が入りました。みなありがたく頂戴
いたしているでござりましょう」
「そうか、若狭と弥左衛門が戻ったら、わしもひとさし舞って見よう。久々で・・・。」
「もうお二人も、程なくこれへ見えられましょう。若狭どのは酒肴を配ったあと、もう一度この下に積み込んだ薪や火薬を見て来ると申しておりましtが」
「そうか、いやみんなよくやってくれた。のう、お方」
「はい・・・・」
「姫たちは、途中で筑前とはすれ違うたが、無事に府中の城へ入ったらしいし、思いおくことはない。あとはただ筑前めをからこうてやれば、それで済む。のう、文荷斎」
「はい、今宵あたり筑前はビクビクものでござりましょう。まさかこうして、戦勝祝いのような大盤
振 る舞
いとは思いもよりませぬでなあ」
「その事よ。想うだけでおかしくなる。が、あの猿めがびっくりするのはこれからだ」
「殿!」
と、お市の方は盃を乾して、良人の前へ差し出しながら、
「筑前が話は、もうおよしなされませ」
「そうか、しては悪いか」
「もはや、筑前もなければ城もない、澄みきって空にかかった月になりとう存じまする」
勝家は何度もうなずいた。やはえいまだこだわりを脱しきれない自分が省みられたのだ」
「止そう。もうせぬぞ、猿めが話は・・・・わしはあやつを相手にせぬのだ」
「さ、お過ごしなされませ。わらわも今宵は、何もかも忘れてお流れをいただきまする」
「よしよし、差そう。さ、この修理が自分で注
ごう。そうじゃ、お方だけではならぬ。みなも乾せ。よいか、権六に昔から、いつも渋面
作って肩肘 張って来たこの修理が、今宵はみなの酌
をしよう。な、許せよ。許してくれよ。わしの意地を貫くために、あの猿めと・・・・」
また秀吉のことを言いかけて、勝家はハハハ・・・・と大きく笑いとばした。
「さ、一世一代の、修理の酌、呑
んだり、呑んだり・・・・」
六十二歳とは思えぬ頑丈な体だったが、それが酔いに任せて立ち上がった姿は、やはり悲しい翳
がしみついている。
勝家の手のついている六人の妾たちの中で、いちばん年取った阿閑
という女が、勝家に盃を渡されるとたまりかねてすすり上げた。
「はて、なんで泣くのだ、こなたは・・・・」
「はい・・・・いいえ、泣きはいたしませぬ。私などは・・・・もう五十路
に近い身、なんで泣きなどいたしましょう。殿お手ずからの酌をいただき、もったいなさの嬉し涙でござりまする」
「ハハハ・・・・閑が、何を言うやら、よいよい、明日になったら、若い者で、落ちたい者は落としてやろう。澄んだ月じゃこの修理は・・・・猿めがことも、城のことも、みな忘れてひっそりと空にかかっている月じゃ。さ、次ぎの者、酌してとらすぞ」
そこへ柴田弥左衛門と、小島若狭が、酒肴を配り終わってあがって来た。 |