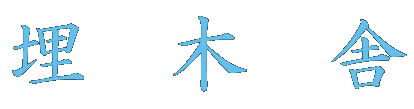茶々姫は、母も共に落ちると聞いて急にそわそわしだしていた。
あるいは、母だけが落ちると言ったのでは、まだ疑ってみたかも知れない。しかし、前田家からの人質も、勝家の妾腹の姫も連れて行くと聞かされると、
(そのせいで、心が変わったのだ・・・・)
自分で自分をうなずかせた。
義理とか意地とかいうことにはすぐに心を動かす母・・・・そう思い込んでいるせいであった。
「では、勝どのも、政どのも共に落ちるのでござりましょうなあ」
「そういたしましょう。修理どのとて、姫たちを助けたい心はいっぱいであろうゆえ」
「では、われらも、母さまと共に、なあ高どのも達どのも・・・・」
「はい、すぐに支度をいたしまする」
二人の妹は、もはや、姉の話の行きがかりなど忘れてしまって立ち上がった。
続いてとどろく銃声が、すっかり彼女たちを狼狽させてしまったせいである。
お市の方は、遺品をそれぞれの身につけさせると、自分でも身支度にかかっていき、そのころから城内の空気は一変していった。
勝家の命で、惣構
えの守備を徹 し、予想のごとく、二、三の丸に全員がこもることに決まったからだった。
いったん城に入った老若男女と郭内
の長屋に住んでいた士卒の家族が、次々に城を出されていった。士卒の妻子はいくらかの金銀をめぐまれて、良人や父を残したまま、親類縁者を頼って離散しなければならなくなったのだ。
最初西南にあがった火の手は、火の暮れ方には十数ヶ所を数えるようになり、それが落日のあとの夜空を呪
わしく彩 りだした。
二、三の丸の郭内は日が落ちてもまだ忙しく動きまわる人の影で息づまるようだった。弾丸よけの竹束をかつぐ者、閉ざした門のうちに杭を打ち込む者、かがり火の用意に走る者、炊き出しの支度にかかる者・・・・
そして──
小島若狭と中村文荷斎
とが、脚絆 にわらじをつけ、笠を持たされた、勝家の姫二人と、利家の娘を連れてお市の方の居間へやって来たのは、もう家の中が暗くなってからであった。
「御台所さま、約束の姫たちを連れて参りました。文荷斎どのが乾門
までお供いたしまする。おざお出ましを・・・・」
そう言った時には、お市の方も、三人の姫たちも、薄暮の窓に寄り添うようにして、夜空を焦がす放火の焔を見つめていた。
「あ、それから、殿はもう、どなたにもお目にかからぬ。堅固でお暮らしあるようにとのお言葉でござりました」
「うけたまわりました。では若狭どのから、殿へ、くれぐれもよろしゅう」
「かしこまってござりまする。乾門の外にはもはや前田家の者が参っておりますはず、若狭は、これにてお別れいたしまする」
「ご大切に。と言うてもなあ・・・・」
「さらばでござりまする」
「では、姫たち、さ、中村どのの後に続いて」
その声で、みんなは文荷斎を取りまくようにして廊下へ出た。
時々あちこちで馬がいままき、罵
り合う切迫した人声が聞こえて来る。
みんなは夢中で階段をおり、それから暗い庭へみちびかれた。 |