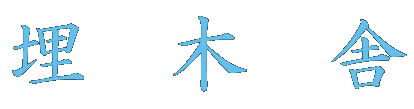光秀は 「馬を曳け」
と命じておいて、危く霽 れた空を見上げながら、天王山の見通せる小丘の上に立った。
(この小山が、天下分け目の場所になったのか・・・・)
その感情が、ジーンと全身をおしつつんで、息苦しいまでの想いであった。
「おお、しきりに山頂に霧が流れている・・・・」
銃声の交錯
はもはや、右も左もなかった。耳をすますと津波のように両軍の喚声までが聞こえてくる。
敵も味方も陣鉦
、太鼓はみな進撃を命じるもので、泥濘の中の格闘が、ほうふつと瞼に浮かんだ。
(この勢いでは夜に入るまでに大勢は決しそうだぞ)
光秀のその観察は適中していた。
天王山へ挑みかかった山手の部隊が、まだ勝因をつかみかねている間に、最精鋭の斎藤利三以下の主力部隊が動揺しだしたのだ。
(はてな?
これはおかしいぞ)
何しろ、鉄砲は撃ち合っても、まだそれが勝敗を決定的にする時代ではない。人間の動きは常に微妙に士気につながり、それが、一瞬にして崩壊の原因ともなればまた勝因ともなってゆく。
「ご注進!」
「どこからじゃ」
光秀はだんだん暗くなってゆく足もとをすかすようにして、太刀を背負い上げたまま、自分の前にひれ伏した注進をうながした。
「早く言え・・・・どこからじゃ」
「川手の津田からにござりまする」
「与三郎が勢は何としたぞ」
「川向こうには筒井勢があるゆえ、安堵
しきっていたのが油断でございました」
「なに油断・・・・」
「はいッ、筒井勢はお味方にあらず、敵と内応しあったに相違ござりませぬ」
「そのような事は訊いておらぬ。敗れたのか与三郎は」
「はい、無念ながら、池田信輝は五千の勢に備えているところへ、加藤光泰は軍勢また二千、無二無三に、川べりより斎藤勢が本隊のうしろまで迂回いたしてござりまする」
「しまった!」
一瞬光秀は、全身の血が凍結してゆくのを感じとった。
勝敗は彼があれほど気を配っていた天王山で決したのではなくて、全く思いがけない川手で決してしまっていた。
「加藤光泰が一隊は、徒歩
にて渡れぬ所まで無数の船にて兵を運び、あっと言う間もござりませぬ。しかも・・・・それを見て、さらに動かぬ筒井勢・・・・敵には船団と筒井の押さえと、二つの備えがござりました」
光秀はもうそのときには、注進に言葉を聞いてはいなかった。
(秀吉めは、何という恐ろしい奴・・・・)
はじめてそれを体で知って、心の底から寒気を覚えた。
彼が、川筋を押えている堺衆や、淀屋などまで操って、船を自在に使っていたことには気がつかなかったが、筒井順慶の存在を、光秀とは全然逆に活用した手腕のほどは、戦慄
しながらも感嘆せずにはいられなかった。
(何という戦上手な・・・・あの猿めは)
そう言えば味方の中央軍はいよいよ動揺を大ききし、太刀打ちの音が、しだいにこの御坊塚へ近づきつつあった。
|