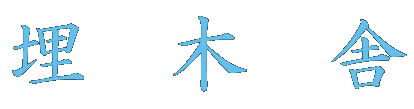家康は近ごろめっきり肥えてきた体を、暑気と臭気にあれられて、もてあつかいかねていた。
むろん、衣類を脱いだり、いぎたなく横になったりできる家康ではなく、堀久太郎の屋敷の、大宝院とは比較にならない質素な書院作りの広間に、きちんと坐って扇を動かしている。
「忠次、今日は右府さま、山から降りて来ねばいいがの」
「なぜでござりまする?」
酒井忠次は、これも朝から何度となく焚かれる伽羅
の煙に閉口して、鼻のまわりに薄黒く環をつくっていた。
「右府さまが山頂の城にござるゆえ、これで済む。もし街を歩かれたら、明智どのがの」
「あ、そのことで、心せねばならぬものでござりまする。まさか、あとで、これほどと思うて捨てたのではござりますまいに・・・・」
家康は、ちらりと眼もとに笑いを見せて、本多平八郎と大久保忠隣を見やった。
「明智どのは、羽柴どのの軍扇の下で働くことに、快
からぬのかも知れぬて」
しかし、その言葉はみんなには咄嗟
にのみ込めなかったらしく、家康もまた、それだけで、そのことには触れなかった。
ただ西南の風が吹きぬけて来るたびに、涼より鼻を蔽わねばならぬ臭気に、顔を見合わせては苦笑をくり返すばかり。そこへ青山与総がやって来て信長の言葉を伝えた。
「ほほう、すると右府さまもご存知であられたのか」
家康は、この臭気を知っていて信長の怒らないのがふしぎな気がした。
(よほど備中の戦に心を痛めているのであろう)
そう言えば滝川一益は関東の厩橋
にとどまり、柴田勝家と佐々
成政 は、越中で魚津
城を囲んで戦っている。
信孝
は阿波に渡らんとして堺
に発ち、信雄 は伊勢に置かねばならぬ。さしもの大兵力もほとんど手一杯の感がなくはなかった。(これでは我慢づよくもならねばならぬか・・・・)
こうして問題の臭気が、ようやく安土に街から消えうせたのは、いよいよ信長が直接家康のために慰安の宴を催すことになっている十八日の朝であった。
この朝家康は、大名各の家臣二十名と、穴山梅雪を伴って総見寺に出向いていった。
一行の到着したときには信長はすでにやって来ていて、
「おお徳川どの、よくぞ参られた。さ、今日は、信長みずからご歓待申すぞ」
頬にたかぶりの紅を見せ、手を取って設けの席へ案内し、それから自分で家康の前へ膳をすえた。
このようなことをする信長をかって見たことはない。それだけに当の家康も、ご馳走役の丹羽五郎左、堀久太郎、長谷川竹丸の面々もかえってシーンと固くなった。
ただ徳川家の家臣だけはこれを見て、わが主君へのなみなみならぬ崇敬と、心の底から感激したのは言うまでもない。
料理は当時としては最上の贅
を尽くして五の膳つきで、やがて宴が終わると、信長は、一同を自身で安土城の見物に案内した。
山頂にそびえた七層の城の豪華さが、いかに彼らの胆をうばったことか。見物が済むと今度は三層の広間で、手ずから徳川家の家臣たちにかたびら二枚ずつを配った。
一枚は国の女房どもへの土産という、心憎いまでこまかい気の配り方であった。 |