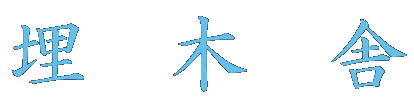「これこれ、取り乱すまいぞ」
金田正祐は声をかけたが、すがりついた女を引き離すことはしなかった。逆に二人に背を向けて、
「静にいたせ」
と周囲をおさえた。
女は奥の老女須賀で、於大の足は思わず停まった。
百合も小笹もいなくなって大奥ではこの女だけが、表裏ない於大の忠僕だったが、その須賀の指さす先を見て、さすがの於大もぎくりとした。
(おお、竹千代が・・・・)
そう思った瞬間に、抱いている女にハッと気づいたのだ。それは乳人
のお貞でもなければ亀女でもなかった。お部屋のお久の方なのだ。お久の方は竹千代をかざすようにして大榎の下に立っている。表情はこれも堅く蒼ざまていた。キラキラと双の眸に光があった。
それだけではない。彼女の右側には六つになる勘六が立っていたし、右手には竹千代と同じ年の恵新が女中の万に抱かれて寄り添っていた。
それは見ようによってはさまざまに受け取られた。
於大に広忠の寵を奪われたお久の方が、わざわざこんどの於大の不幸を嘲笑っていりようのもとれたし、その反対にも取れた。
(あなたの苦しさはわかります)
しかし、その同情にしては頬の色が蒼すぎる。歩くともなくついて来た老臣たちの中にも顔色を変えた者がある。
於大の大きく見張った眼に、まざまざと心の嵐が映じてゆくからであった。
於大は呼吸
をしなかった。まばたきもしなかったし歩きだしもしなかった。
といって、於大は、もうお久の方を見ているのではなかった。口では強く言いながら、わが子の姿を前にして、骨も血も凍りそうな衝撃
をうけたのだ・・・・
竹千代は依然として丸々と肥っていた。小さな拳は今日も堅く握られて、手首は深くくびれている。時々空を見たり、人を見たり、お久の方の耳朶あたりを見たりする。眼は活
きいきと輝いて上を見るたびに鹿爪らしい額に皺が寄った。
むろんまだ母を見覚えて記憶にとどめる年齢ではない。が成人した後に、こうして去って行くこの母を、いつか思い出す日があるであろうか・・・・?
於大は出かかった涙を瞼の裏で乾かした。それが今日只今の必死の母の愛情だった。
(あの子の母は・・・・)
と他人に言われたくなかった。自分の見栄ではない。あの母から生まれた子ゆえと蔑
まれたら、悔 いは生涯あとを曳く。
(これが母と子のこの世で会う最後の日・・・・)
そう思うと、もう於大は感情に勝てなかった。あわてて視線を榎にそらした。いっそう大きく眸を開いて、また涙を乾かしながら、お久が何ゆえこうして、竹千代と共に自分を見送ってくれたかに思考をそらそうと努力した。
於大の気性では、これがお久の仕返しとは取れなかった。竹千代を盛り立て、兄弟心を合わせて睦んでくゆえ、安心してくれるようにと、必死で告げている気がした。
「須賀、お久どににくれぐれもよろしく伝えてくりゃれ」
於大は足もとに巻き崩れている須賀に言って、それから菅正門にかかっていった。 |