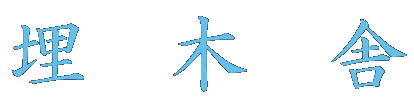竹垣に一太刀あびせた広忠の顔はまっ蒼であった。手も膝もブルブル震えている。また太刀をふりかぶった。
「えっ!」
バサッと乾いた音がしてこんどは結び目の十字が切り離された。
物音に驚いて離れの障子がうちから開いた。びっくりした於大の顔がほの暗い灯りにういて、その眸だけがきらきらと活きている。
「新八めが、思うままに振る舞えよと申した。小賢
しい!」
「殿!」
「予とて思うままに振る舞いたいは山々じゃ。が、予が思うままに振る舞うたら、一族郎党はなんとなる」
「殿、お声が・・・・」
高いと言おうとしたとき、広忠の太刀は三度振られた。四ツ目垣はそこだけ四角に道を開いて、足もとの草におりた露が灯りにきらめいた。
「予はこの垣根など我慢ならぬ。思うままにせよというゆえ、切り払ったのだ!」
於大は思わず眼を伏せた。狂ったような広忠の昂
ぶりが、どこから来るかを於大はもう知っている。
(お痛わしい殿・・・・)
いつも自分の弱気と闘い、家臣と闘う。しかもその闘いを続けるにはあまりに細い広忠の神経だった。
思うては悔い、悔いては怒り、怒ってはまた反省して、いつも重荷の波にゆられる。
おそらくここに垣を結わせたのも今川家の使者をはばかってのこの広忠の指図であったろう。そしてその弱さにいま自分で腹を立てて太刀を振っている。於大はそのあとまた悔いるのではなかろうかと思うと、こうした時世に松平党の大将に生まれ合わせた広忠の悲劇に胸が痛んだ。
広忠は太刀を小姓に渡した。まだ手も膝もわなわなrと震えている。硬直した歩き方でつかつかと於大のいる縁に近づいた。そしてそのうしろにうやうやしく従
いて来る小姓を見ると、
「退れッ! 誰がついて参れと申した」
もう一度全身を波打たせて吠えるように叱りつけた。その声はむろん雅楽助の屋敷中にひびいているに違いない。しかしどこからも物音ひとつしなかった。
シーンと静まり返って、この若い当主の心にのたうつ苦悶
を弔 っているようだ。小姓がこれも足音をはばかって去ってゆくと、
「於大・・・・」
広忠は眼の前にうなだれている於大にはじめて小さく声をかけた。はげしい運命への怒りが去って、底なしの淋しさが、霧のように沸きはじめてきたらしい。
「わしはな、今宵ばかりは堂々とそなたに会いたかった。誰に気も兼ねず、大手をふって会いたかった」
「殿!
うれしゅうございます」
「よいか、よく見ておけよ。これが三河に父祖の遺業をつぐ岡崎城の城主が奥へ通う姿なのじゃ」
そこまで言って、またいちだんと声をおとし、
「竹千代と申す世継ぎの母者、この世でたった一人の・・・・愛おしいおことのもとへ通う姿じゃ」
「殿・・・・」
於大は思わず走りよって、その手にすがった。額には鉛色の汗が見えたが、その手は細く、心に沁みる冷たさだった。 |