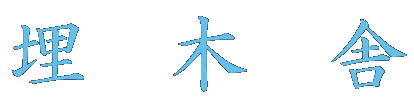この屋敷に預けられるとき広忠は於大に言った。
「── 予がなぜ雅楽助が屋敷を選んだか、お方にはそれが分るであろう」
細い面に、怒りと悲しみを刻んだまま、於大の肩を強く揺すった。
もう於大には広忠の心のすみまでわかっていた。広忠は、刈谷の義兄、水野下野の織田随身を聞いたとき、精一杯の冷静さで次に打ち寄せる悲劇の波を避けようとした。
「──
お方は竹千代の母。予の妻じゃ。その妻を奥から追う予の心は汲めるであろう」
広忠は、今川方から苦情の出る前に、先手を打って於大を雅楽助に預けたのだ。すすんで、遠ざけて、今川家に乗ずる口実を与えまいとする。於大はその行為の底に滴
る良人の愛情をかみしめた。
そしてその行く先を雅楽助の屋敷に求めたのは、広忠自身、於大のもとへ忍ぶ日のある事をおもんばかってのことらしかった。
この忠実な老臣は、二人の密かな愛情を、どこへも洩らす怖れはない。
事実ここに預けられてからも五日に一度、七日に一度はしのんで来た。
奥では大勢の侍女の眼があったが、ここでは小婢
一人であった。広忠にしても於大にしても、そのような環境でのびにびと抱き合うのは始めてだった。
人生の波はいつも悲しみと喜びを皮肉に交えて押し寄せる。於大はここへ来てからはじめて身も心も、悲しくうつろう女の幸福を知らされた。
広忠も褥
の中でそれを言った。堰 かれて忍ぶ切なさが、まことの夫婦の味ともらした。
「離すものか。お方は竹千代の母なのじゃ。この広忠の妻なのじゃ」
それだけに、この離れの四週に竹垣が結いつけられても、於大はさして心配はしていなかった。駿府の使者への思惑からであろうと忍ぶ日の広忠の不便を描くときすらあった。
ところが母は、思いがけないことを言う。いや、思いがけないことではなくて、それはどこかで絶えず怖れていたことではあったが・・・・
広忠がまた忍んで来る。
そのときには泣くなという。母にとっては一人の良人、水野忠政の娘ならば、夫婦の縁は断たれても見苦しいことをして笑われまいぞと言っている。
日が落ちかけて、残照がかっと強く庭木にあたり、木斛の向こうの母の姿は光の中に溶けている。於大以上に、この知らせを持って来た母の方が切ないに違いない。
それにしても、こうして遠慮している夫婦を酷
たらしく割 いてゆくものは何であろうか?
今川義元とは、そのような人の情を解さぬ人か。
「お屋敷、もう私は戻りますぞえ」
しばらくして華陽院は頭巾の端で涙をい拭いている気配であった。本丸ではいよいよ急調子に小鼓が聞こえて来る。
「そなたはいなくなってもこのばばは岡崎へ残っている。竹千代はこのばばが、じっと見守っているほどに、お屋敷はのう・・・・」
そういうと、こんどは語尾があたりをはばからぬ嗚咽になった。於大は、この時ほど小鼓の音を憎いものに聞いたことはなかった。
|