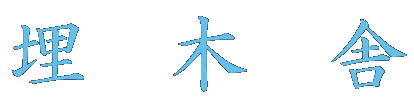日脚はめっきり短くなった。手水
石 にかさぶった木斛
の葉の下に猫が仔をつれて出て来ている。
暮れる前のひと時を於大は縁にたたずんで、仔を舐
めてやっている猫の動作に眼をおとした。
本丸の曲輪を越えて小鼓の音が聞こえ、庭を隔てた書院の障子はひっそりと閉まっている。
城内といってもここは三の丸と堀をへだてたはずれであった。
酒井雅楽助正家の屋敷なのである。三年前に於大は刈谷からこの家に迎えられた。そのときはまだ草も芽ぶかぬ早春だったが、どこかにキラキラと期待の星が光っていた。
最初に通されたのはこの向かいの書院であった。そこで於大は母の華陽院に対面し、まだ見ぬ広忠の気性やら、新しい妻の心得やらを聞かされた。
(そうだ。あのときは十四であった・・・・)
それがいまは十七歳になり、迎えられる人ではなくて、この屋敷の小さな離れに四ツ目垣で結いこめられた人になっている。
一昨日、駿府から使者が着いた時、老臣たちは協議の上、夫婦揃って迎えるようにと指図した。於大は久しぶりにいそいそと良人に寄り添って本丸の人になったが、それがかえっていけなかった。
顔色が悪いとしりぞけられ、再びこの離れに下がってくると、雅楽助の家臣たちが出入り口のない四ツ目垣を結びに来た。
黒染めの棕梠
縄 でうつむき勝ちに垣を結ぶ家臣たちは、於大を見るとあわてて顔をそむけてゆく。誰も彼もが泣いているとわかると、於大はこの処置が誰の命かと、改めて訊ねてみる勇気はなかった。
小笹も百合ももういない。
ただ一人つけられた下婢は、まだ話もできぬ十二歳の小娘で、出口のないこの離れへ、ずかずかとやって来るのは畜生の猫ばかりであった。
しかもその猫は仔を連れている。追う人がないので、長々と手足をのばし、四匹の仔たちに乳房をふくませてしきりに毛並みをそろえてやる。
その光景を見ていると於大の胸はいっぱいになった。
まだ片言で母とは呼べず、ハバチャとあやしく口を動かす竹千代の姿が、瞼
いっぱいにひろがるのだ。
天野の妻女、乳母のお貞の乳がよくあい、竹千代は地表を破った孟宗竹
に似た太り肉 だった。
いかにも鹿爪
らしい横皺を額にきざんで、両の拳を堅く握っている。切れ長の眼もと、大作りの鼻、丸くくびれた顎
などは祖父の水野忠政そくりだった。
その竹千代はいま三の丸にいる。一昨日ちらと見かけたとき、また目立って大きく育っていたが・・・・と、思ったとき、木斛の向こうの芙蓉
のかげから、
垣根越しにあたりをはばかる母の華陽院の声であった。 |