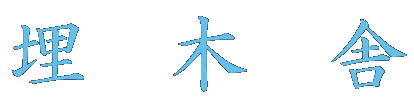「ああ、うららかなよいお天気じゃ」
産屋を訪れた足音の主は、入り口でのびやかにつぶやいた。お久の父の松平左近乗正だった。
産屋の明くまでの二十一日間は火の汚れを嫌って男たちは産屋に入らない。
外から声をかけに寄ってくれたのであろうと、褥
の上でお久はそっと顔を立てた。
「まだ男が訪れてはならぬのじゃが・・・・」
いくぶん酒が入っていると見え、乗正は独りごちた。
「こうめでたさが続いては入らぬわけにも参るまいて。南無秋葉大明神許させたまえ」
雪どけの泥をはらって木履をぬぐと、
「わしは今日は男ではない。産屋見舞いの女子じゃ女子じゃ」
さらりと戸があいて、ハッハッハッと陽気な笑いを浴びせて来た。
「勘六どのはいたって元気でな。大給
の館で婆どのと戯れてござる。心配することは少しもない」
お久は大きく眸をあけて、うなずきもしなかったし、笑いもしなかった。今父に言われるまで、祖父の家に預けられていた勘六のことを思い出さずにいた。
乗正は言葉づかいとは反対に、姿勢だけはひどくきちんといかめしかった。
彼は先ず勘六のことを娘に告げると、それから膝の下へ両手を置いてわが二人目の孫と対面した。
「おお・・・・殿によく似ておる」
両手をつかえたままで乗正の額から眼のくまにいっぱい皺がうかんでいった。
「この児もまた竹千代殿と日を同しゅうして生まれるとは何というふしぎであろうか」
語尾があやしくうるんだので、お久はびっくりして父を見直した。一族の中では凡庸
な誠実さをある者には買われ、ある者には蔑
まれている父であった。その父が自分の生んだ子供を見て涙ぐんでいる。父だけに自分の口惜しさやる瀬なさが通じるのだ・・・・そう思うとお久の枕は新しい涙で濡れた。
「勘六どのは、泣きませんでしたか」
「おお、連れて来られた日からすっかり館の奥の虎が気に入ってな。虎のそばに夜具を敷かせて休んだわ」
「ホホホ」
と部屋の隅で万が笑った。笑ったあとでハッと形を正したが、乗正の動作には、どこかにそんな和
やかさとおかしさがあふれていた。
「ハハハハ、女中どのまで笑うているわ。いや笑うがよい。笑うがよい。兄者の勘六どのが虎の絵と寝ているときに、その弟は生まれたのじゃ・・・・」
お久の頬ははじめて微かにほころびた。
(そうであった・・・・わが子には勘六という兄があった)
兄弟二人で力を合わせて生きる日は竹千代より先に来よう。と思ったときに、父は持参の扇子を持って、びしりと自分の膝をたたいた。
「虎の威に戯れる兄、寅年の寅の刻に生まれた弟、何もかもめでたづくめじゃ。この二人が心を合わして普賢菩薩の化身におわす竹千代どのを輔佐したら、おそらく天下に敵はあるまい。これだけ大きな瑞祥
が重なるとはよくよくのこと。松平家は万々歳じゃ。ああ、笑うがよい。笑うがよいぞハハハ・・・・」
お久は思わず顔をそむけた。
やはり父はお久の心など微塵
もわかっていなかったのだ。 |